
「菜園家族」構想
「菜園家族」構想とは
地球規模で展開される“巨大化”への道の弊害と行き詰まりが浮き彫りになった今、私たちは、あらためて家族と家族小経営のもつ優れた側面を再評価し、それを今日の社会にどう位置づけ、どのように組み込むべきかを、つまり、人間を育む究極の場としての「家族」と「地域」をいかにして再構築すべきかを、真剣に考えるよう迫られています。
18世紀イギリス産業革命以来、大地から引き離され根なし草同然の「賃金労働者」となった人間の社会的生存形態は、今ではすっかり人々の常識となってしまいました。
しかし、やがてこれも、21世紀世界が行き詰まる中で、新しく芽生えてくるものにその席を譲らざるをえなくなるにちがいありません。
「菜園家族」は、こうした時代の転換の激動の中から必然的にあらわれてくる、人間生存の新たなる普遍的形態なのです。
「菜園家族」構想は、まさにこの新たなる形態に人間本来の豊かさと無限の可能性を見出し、人類究極の夢である大地への回帰と、自由・平等・友愛の“高度自然社会”への道を探ろうとしています。
私たちは、2000年5月に小冊子『週休五日制による三世代「菜園家族」酔夢譚』(Nomad刊)を刊行して以来、その後の時代状況や地域の現実を組み込みつつ、この「菜園家族」構想を理論的にもより深めながら数次にわたって検討を加え、その成果を順次、出版してきました。
以下に掲げる一連の拙著書が、自然と人間、人間と人間との関係をあらためて見つめ直し、18世紀イギリス産業革命以来、ついに人々を苦悩と破滅の淵へと追いやってきたこの呪われた近代をのり超え、遥かな地平へと誘う21世紀の新たな社会構想へのささやかな試論になればと願っています。
「菜園家族」関連の拙著
最新刊『グローバル市場原理に抗する 静かなるレボリューション ―自然循環型共生社会への道―』
海図なき時代に贈るこの一冊
人類の目指す終点は
遙かに遠い未来である
それでも、それをどう描くかによって
明日からの生き方は決まってくる
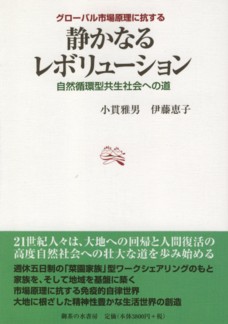
| 題名 | グローバル市場原理に抗する 静かなるレボリューション ―自然循環型共生社会への道― |
| 著者 | 小貫雅男・伊藤恵子 |
| 出版社 | 御茶の水書房 |
| 発行年月 | 2013年6月 |
| 判型・ページ | A5判、369ページ |
| 定価 | 本体3,800円+税 |
| ISBN | 9784275010353 |
21世紀人々は大地への回帰と人間復活の高度自然社会への壮大な道を歩み始める。
週休五日制の「菜園家族」型ワークシェアリングのもと、家族を、そして地域を基盤に築く市場原理に抗する免疫的自律世界、大地に根ざした精神性豊かな生活世界の創造。
本書に込められたメッセージ
―今こそパラダイムの転換を―
底知れぬ
深い闇に沈む
閉塞の時代
私たちはあまりにも目先の瑣事
その場凌ぎの処方箋に惑わされ
そこから一歩も抜け出せずにいる。
今、私たちにもっとも欠けているものは
元々あったはずの人間の素朴さであり
確かな意志をもって
遠い不確かな未来へ挑む
精神なのではないか。
騙されても騙されても・・・
騙されても騙されても、それでもまた繰り返し騙される。人々はそんな不甲斐なさに打ち拉がれ、どうしようもない無力感と政治不信に陥っていく。その一方で、「アベノミクス」なるものの実体のない束の間のつくられた円安・株高に淡い期待を寄せ、浮き足立ち酔い痴れる。
さんざんそうさせられた挙句に、またもや「選挙」だと言うのである。私たちは、何とも不条理で不気味な時代に生きている。
忌まわしい時代に引きずり込まれていく
かつてもそうだったし
いつの世になっても
そうなのであろうか。
3年も経たないうちに
あの過酷事故を
すっかり忘れたかのように
金儲けのために
原発を輸出し
原発再稼働をおしすすめ
他方では抑止力のためだと
なんやかやと屁理屈をこね回し
時代の新たな装いを纏って
お国のため
自衛のため
諸国民の共栄のためにと
美辞麗句を並べ立て
日本国憲法の精神を踏みにじり
偏狭なナショナリズムを煽り
かつての富国強兵路線へと
急転回を遂げていく。
密かに財界や「死の商人」の片棒を担ぐ
お偉い政治家の殿方よ
本当に心底から
そう思っておられるのであれば
それはそれで
勝手に語るがいい。
しかし、このことだけは
しかと肝に銘じてほしい。
自らは戦場に行かず
身を投げ出す覚悟すらないのに
ご高邁な精神を満足させるために
人様を巻き添えにすることだけは
どうかやめてもらいたい。
大義のない
そんな嘘っぽい
卑小な思想は
誰だって
まっぴらごめんなのだ。
他国を敵視し、人々を煽り
「お国のために戦った兵隊さんよ、ありがとう」と
子供たちに唱歌をうたわせ
国民を戦場へと駆り立てた
あの熱狂の時代と
一体、本質的に
どこがどう違うのであろうか。
渦中にいる
小さき弱きものたちは
ずる賢い甘い言葉に惑わされ
気づかないとでも思っているのであろうか。
何とも忌まわしい時代に
ずるずる引きずり込まれていく。
この国の深刻きわまりない病弊を見る
大胆な「金融緩和」、放漫な「財政出動」(防災に名を借りた大型公共事業の復活)、巨大企業主導の旧態依然たる輸出・外需依存の「成長戦略」。とうに使い古されたこの「三本の矢」で、相も変わらず経済成長を目指すという「アベノミクス」なるもの。
戦後六十余年におよぶ付けとも言うべき日本社会の構造的破綻の根本原因にはまともに向き合おうともせずに、ただひたすら目先のデフレ・円高脱却、そして景気の回復をと、選挙目当てのその場凌ぎの対症療法を今なお性懲りもなく延々と繰り返す。むしろこのこと自体に、この国の政治と社会の深刻な病弊を見るのである。
今こそパラダイムの転換を
資本主義経済固有の不確実性と投機性、底知れぬ不安定性。とりわけ人間の飽くなき欲望の究極の化身とも言うべき、今日の市場原理至上主義「拡大成長路線」の虚構性と欺瞞性。そして何よりも目に余る不公正と非人道性、その残虐性は、いずれ克服されなければならない運命にある。
歴史の大きな流れの一大転換期にあって今まさに必要としているものは、その場凌ぎの処方箋などではない。社会のこの恐るべき構造的破綻の本当の原因がどこにあるのか、その根源的原因の究明と、それに基づく長期展望に立った社会経済構造の深部におよぶ変革に、誠実に挑戦することではないのか。
現代賃金労働者という人間の社会的生存形態
大地から引き離され、根なし草同然となった現代賃金労働者という名の人間の社会的生存形態は、今ではすっかり常識となった。
こうした中で、人間は自然からますます乖離し、自らがつくり出した社会の制御能力を喪失し、絶えず生活の不安に怯えている。高度に発達した科学技術によって固められた虚構の上に築かれた危うい巨大な社会システム。人間は、自然から遮断されたこのごく限られた、僅かばかりの狭隘できわめて人工的な空間に幽閉され、生来の野性を失い、精神の虚弱化と欲望の肥大化が進行していく。
今あらためて大自然界の生成・進化の長い歴史のスパンの中に人類史を位置づけ、その中で、18世紀イギリス産業革命を起点とする近代を根本から捉え直し、未来社会を展望するよう迫られている。
近代を超克する21世紀の未来社会論の構築を
大地への回帰。この素朴とも言うべき哲理こそが、行き場を失い混迷に陥った今日の社会を根本から建て直す指針となるのではないか。
大地への回帰、これを空想に終わらせることなく、現実のものとするための大切な鍵は何か。本書では、近代のはじまりとともに生み出され、長きにわたって社会の基層を構成し、今ではすっかり常識となった賃金労働者という人間の社会的生存形態そのものに着目し、それ自身を根本的に捉え直すことによって、19世紀以来の未来社会論が今日まで不覚にも見過ごしてきた問題を浮き彫りにし、そこから社会構築の新たなる道を探ろうとしている。
それは、近代の歴史過程で大地から引き離された家族に、生きるに最低限必要な生産手段(農地や生産用具など)を再び取り戻すこと、つまり現代賃金労働者と生産手段との「再結合」を果たすことである。これはすなわち、21世紀の新たなる人間の社会的生存形態の創出を意味している。これによって、相対的に自給自足度が高く、市場原理に抗する免疫力に優れた「菜園家族」が形成される。それはいまだかつて見ることのなかった、精神性豊かな、慈しみ深い、しかも大地に根ざして生きるおおらかな、素朴で繊細にして強靱な人間の誕生でもある。
足もとの暮らしの中から未来への芽を育む
ガンジーはイギリス資本主義の植民地支配と闘う中で、真の独立・自治(スワラージ)は単なる権力の移譲ではなく、インド再生の鍵は農村にあるとし、個人の自立と民族の独立の象徴として紡ぎ車を選び、村落の手仕事の伝統をインド経済の基礎に据え、スワデーシ(地域経済)を復活させようとした。
今こそこの深い思想の核心を「弱者」のみならず、むしろ先進資本主義国私たち自身の社会に創造的に生かす時に来ているのではないか。
かつて人々は、現実社会の自らの生産と生活の足もとから未来へつながる小さな芽を慈しみ、一つ一つ育み、しかも自らのためには多くを望まず、ただひたすらその小さな可能性を社会の底から忍耐強く静かに積み上げてきた。人間は、このこと自体に生きがいと喜びを感じてきたのである。本来これこそが、生きるということではなかったのか。
大地に生きる人間のこの素朴で楽天主義とも思える明るさの中に、明日への希望が見えてくる。これはまさに「静かなるレボリューション」の真髄にほかならない。
自由闊達な対話からはじまる草の根の本物の民主主義
思えば、長きにわたって人々を愚弄してきた偽りの選挙制度のもとで、私たちは「選挙」だけに頼る「政治」にあまりにも安易に幻想を抱いてきたのではなかったのか。かくも歪められた「政治」のあり方を民主主義と思い込み、この両者を根本から履き違えてきたのではなかったのか。今こそ覚悟を決め、思考停止と「お任せ民主主義」から抜け出さなければならない時に来ている。
自らの頭で自由に考え、他者を尊重し、ねばり強く対話を重ね、めざすべき21世紀の未来像を共有する。この長期にわたる苦難と試練のプロセスの中からこそ、自らの力量を涵養し、自らの手で、自らの未来を切り開くことができるのである。これこそが民主主義の真髄ではなかったのか。
長きにわたる閉塞状況から忌まわしい反動の時代へとずるずると急傾斜していく中、それでも怒りを堪え、じっと耳を澄ませば、新しい時代への鼓動が聞こえてくる。たとえそれが幽かであっても、信じたいと思う。そして対話への期待も、その意義も、未来への光もそこに見出したいのである。
草の根の本物の民主主義の復権、そして21世紀のあるべき未来像をもとめて止まないひたむきな対話の一角に、ささやかながらも本書が加わることができるならば、こんなうれしいことはない。
ホームページのリニューアルに際して
著者 小貫 雅男・伊藤 恵子
目次
- プロローグ ― 東日本大震災から希望の明日へ (17)
- あのときの衝撃を一時の「自粛」に終わらせてはならない (18)
- 「原発安全神話」の上に築かれた危うい国 (22)
- 誰のための復興構想なのか (23)
- 続々と現れる復興への目論見 (26)
- 復興構想私案の震源地はここにあり (29)
- 財界の意を汲む復興構想の末路 (31)
- 21世紀未来像の欠如と地域再生の混迷 ― 上からの「政策」を許す土壌 (36)
- 新たな21世紀の未来社会論を求めて ― 本書の目的と構成 (38)
- 今なぜ近代に遡るのか (44)
- 世界で初めての恐慌と悪循環 (49)
- 人類始原の自然状態 (55)
- 自然状態の解体とその論理 (59)
- 新しい思想家・実践家の登場 (64)
- ニューハーモニー実験の光と影 (73)
- 資本主義の発展と新たな理論の登場 (77)
- マルクスの経済学研究と『資本論』 (83)
- 資本の論理と世界恐慌 (90)
- 人類の歴史を貫く根源的思想 (95)
- マルクスの未来社会論 (98)
- 導き出された生産手段の「共有化論」、その成立条件 (103)
- 今こそ19世紀理論の総括の上に (111)
- マルクス「共有化論」、その限界と欠陥 ― 時代的制約 (114)
- 人は明日があるから今日を生きる (126)
- 今こそ19世紀未来社会論に代わる私たち自身の21世紀未来社会論を (127)
- 新たな歴史観の探究を (129)
- 未来社会論に欠かせない「地域研究」の視点 ― 新たな地域未来学の確立 (132)
- いのち削り、心病む終わりなき市場競争 (135)
- 「二つの輪」が重なる家族が消えた (138)
- 高度経済成長以前のわが国の暮らし ― かつての森と海を結ぶ流域地域圏 (139)
- 森から平野へ移行する暮らしの場 (141)
- 歪められ修復不能に陥ったこの国のかたち (143)
- 「家族」と「地域」衰退のメカニズム (144)
- 再生への鍵 ― 家族と地域を基軸に (146)
- 「家族」の評価をめぐる歴史的事情 (149)
- 人間の個体発生の過程に生物進化の壮大なドラマが (151)
- 母胎の中につくられた絶妙な「自然」 (152)
- 人間に特有な「家族」誕生の契機 (154)
- 「家族」がもつ根源的な意義 (157)
- 人間が人間であるために (160)
- 生産手段の分離から「再結合」の道へ ―「自然への回帰と止揚」の歴史思想 (165)
- 週休五日制のワークシェアリングによる三世代「菜園家族」構想 (168)
- 世界に類例を見ないCFP複合社会 ― 史上はじめての試み (173)
- CFP複合社会の特質 (177)
- “菜園家族群落”による日本型農業の再生 ― 高度な労農連携への道 (181)
- 農地とワークの一体的シェアリング ― 公的「農地バンク」、その果たす役割 (188)
- 草の根民主主義熟成の土壌 ― 森と海を結ぶ流域地域圏の再生 (194)
- ふるさと ― 土の匂い、人の温もり (204)
- 甦るものづくりの心、ものづくりの技 (213)
- 土が育むもの ― 素朴で強靱にして繊細な心 (217)
- 家族小経営の歴史性と生命力 (221)
- 非農業基盤の家族小経営 ―「匠商家族」 (225)
- 「匠商家族」とその協同組織「なりわいとも」 (229)
- 「なりわいとも」と森と海を結ぶ流域地域圏の中核都市 (233)
- 「なりわいとも」の歴史的意義 (238)
- 前近代の基盤の上に築く新たな「協同の思想」 (242)
- 高度経済成長が地域にもたらしたもの (244)
- 今日の歪められた国土構造を誘引し決定づけた『日本列島改造論』 (247)
- 『日本列島改造論』の地球版再現は許されない (252)
- 「菜園家族」の創出は、地球温暖化を食い止める究極の鍵 (260)
- 原発のない低炭素社会へ導く究極のメカニズム ― CSSK方式 (262)
- CFP複合社会への移行を促すCSSKメカニズム (263)
- CSSK特定財源による人間本位の新たなる公共的事業 (265)
- 本物の自然循環型共生社会をめざして (268)
- 資本の自己増殖運動と科学技術 (271)
- 資本の従属的地位に転落した科学技術、それがもたらしたもの (272)
- GDPの内実を問う ― 経済成長至上主義への疑問 (275)
- 資本の自然遡行的分散過程と「菜園家族」の創出 (277)
- 新たな科学技術体系の生成・進化と未来社会 (281)
- 今こそ「成長神話」の呪縛からの脱却を (286)
- いまだ具現されない“自由・平等・友愛”の理念 (289)
- スモール・イズ・ビューティフル ― 巨大化の道に抗して (295)
- 果たして家族と地域の再生は不可能なのか ― 諦念から希望へ (298)
- 人々の英知と固い絆と耐える力が地域を変える (304)
- 未踏の思考領域に活路を探る (310)
- 人間の新たな社会的生存形態が、21世紀社会のかたちを決める (313)
- 自然界を貫く「適応・調整」の普遍的原理 (315)
- 自然法則の現れとしての生命 (319)
- 自然界の普遍的原理と21世紀未来社会 (322)
- CFP複合社会を経て高度自然社会へ ― 労働を芸術に高める (326)
- さいごに確認しておきたいいくつかの要諦 (330)
- 北国、春を待つ思い (336)
あとがき (351)
引用・参考文献一覧 (355)
閉じる
はしがき ―解題にかえて
資本主義経済固有の不確実性と投機性、底知れぬ不安定性。とりわけ人間の飽くなき欲望の究極の化身とも言うべき、今日の市場原理至上主義「拡大成長路線」の虚構性と欺瞞性。そして何よりも目に余る不公正と非人道性、その残虐性は、いずれ克服されなければならない運命にある。
2013年1月16日、アルジェリア南東部、サハラ砂漠のイナメナスの天然ガス施設で突如発生した人質事件は、わずか数日のうちに政府軍の強引な武力制圧によって凄惨な結末に終わった。
その後、メディアを賑わす話題は、この種の事件の今後の対策へと収斂していく。現地住民の立場をも視野に入れた公平にして包括的な本質論はほとんど見られず、もっぱら内向きの議論に終始する。こうした中、1月28日、安倍首相は衆参両院の本会議で内閣発足後初めての所信表明演説を行った。演説の冒頭、アルジェリア人質事件に触れ、「世界の最前線で活躍する、何の罪もない日本人が犠牲となったことは、痛恨の極みだ」と強調。「卑劣なテロ行為は、決して許されるものではなく、断固として非難する」とし、「国際社会と連携し、テロと闘い続ける」と声高に叫び胸を張る。
一方的に断罪するこうした雰囲気が蔓延すればするほど、国民もわが身に降りかかるリスクのみに目を奪われ、事の本質を忘れ、ついには軍備増強やむなしとする好戦的で偏狭なナショナリズムにますます陥っていく。こうした世情を背景に、為政者は在留邦人の保護、救出対策を口実に、この時とばかりに自衛隊法の改悪、集団的自衛権の必要性を説き、憲法改悪を企て、国防軍の創設へと加速化していく。
このような時であるからこそなおのこと、センセーショナルで偏狭な見方を一転しなければならない。当該現地の民衆が置かれている立場に立って、わが身の本当の姿を照らし出し、この事件を深く考えてみる必要があるのではないだろうか。
他国の荒涼とした砂漠のただ中に、唐突にもここはわが特別の領土だと言わんばかりに、あたかも治外法権でも主張するかのように、頑丈で物々しい鉄条網を張りめぐらしたミリタリーゾーン。その中で軍隊に守られながら他国の地下資源を勝手気ままに吸い上げ、現地住民の犠牲の上に「快適で豊かな生活」を維持しようとする先進諸国。一方現地では、外国資本につながるごく一部の利権集団に富は集中し、風土に根ざした本来の生産と暮らしのあり方はないがしろにされる。圧倒的多数の民衆は貧窮に喘ぎ、外国資本と自国の軍事的強権体制への反発を募らせ、社会に不満が渦巻いていく。「反政府武装勢力」、そして各地に持続的に頻発するいわば「一揆」なるものは、資源主権と民族自決の精神に目覚めたこうした民衆の広範で根強い心情に支えられたものなのではないのか。これを圧倒的に優位な軍事力によって、強引に制圧、殲滅する。
まさにこの構図は、今にはじまったことではない。アフガニスタンおよびイラク、イランをはじめとする中東問題が、再び北アフリカへと逆流し、さらには世界各地へと拡延していく。こうもしてまで資源とエネルギーを浪費し、「便利で快適な生活」を追い求めたいとする先進資本主義国民の利己的願望。それを「豊かさ」と思い込まされている、ある意味では屈折し歪められた虚構の生活意識。この欺瞞と不正義の上にかろうじて成立する市場原理至上主義「拡大成長路線」の危うさ。この路線の行き着く先の断末魔を、この人質事件にまざまざと見る思いがする。
はるか地の果てアルジェリアで起こったこの事件は、今までになく強烈にこれまでの私たちの暮らしのあり方、社会経済のあり方がいかに罪深いものであるかを告発している。と同時に、私たちの社会のあり方が、もはや限界に達していることをも示している。「拡大成長路線」の弊害とその行き詰まりが白日の下に晒され、誰の目にも明らかになった今、18世紀イギリス産業革命以来、二百数十年にわたって拘泥してきたものの見方、考え方を支配する認識の枠組み、つまり近代の既成のパラダイムを根底から転換させない限り、どうにもにもならないところにまで来ている。
大地から引き離され、根なし草同然となった現代賃金労働者(サラリーマン)という名の人間の社会的生存形態は、今ではすっかり常識となった。一方こうした中で、人間は自然からますます乖離し、自らがつくり出した社会の制御能力を喪失し、絶えず生活の不安に怯えている。高度に発達した科学技術によって固められた虚構の上に築かれた危うい巨大な社会システム。人間は、自然から遮断されたこのごく限られた、僅かばかりの狭隘できわめて人工的な空間に幽閉され、生来の野性を失い、精神の虚弱化と欲望の肥大化が進行していく。今あらためて大自然界の生成・進化の長い歴史のスパンの中に人類史を位置づけ、その中で近代を根本から捉え直し、未来社会を展望するよう迫られている。
しかし、わが国の現状はどうであろうか。大胆な「金融緩和」、放漫な「財政出動」(防災に名を借りた大型公共事業の復活)、巨大企業主導の旧態依然たる輸出・外需依存の「成長戦略」。とうに使い古されたこの「三本の矢」で、相も変わらず経済成長を目指すという「アベノミクス」なるもの。戦後六十余年におよぶ付けとも言うべき日本社会の構造的破綻の根本原因にはまともに向き合おうともせずに、ただひたすら当面のデフレ・円高脱却、そして景気の回復をと、選挙目当てのその場凌ぎの対症療法を今なお性懲りもなく延々と繰り返す。むしろこのこと自体に、この国の政治と社会の深刻な病弊を見るのである。
歴史の大きな流れの一大転換期にあって今まさに必要としているものは、その場凌ぎの処方箋などではない。社会のこの恐るべき構造的破綻の本当の原因がどこにあるのか、その根源的原因の究明と、それに基づく長期展望に立った社会経済構造の深部におよぶ変革に、誠実に挑戦することではないのか。
大地への回帰。この素朴とも言うべき哲理こそが、行き場を失い混迷に陥った今日の社会を根本から建て直す指針となるのではないか。大地への回帰、これを空想に終わらせることなく、現実のものとするための大切な鍵は何か。本書では、近代のはじまりとともに生み出され、長きにわたって社会の基層を構成し、今ではすっかり常識となった賃金労働者という人間の社会的生存形態そのものに着目し、それ自身を根本的に捉え直すことによって、19世紀以来の未来社会論が今日まで不覚にも見過ごしてきた問題を浮き彫りにし、そこから社会構築の新たなる道を探ろうとしている。
具体的には、本編第三章(「菜園家族」構想の基礎)で述べることになる週休五日制の「菜園家族」型ワークシェアリングによって、近代の歴史過程で大地から引き離された家族に、生きるに最低限必要な生産手段(農地や生産用具など)を再び取り戻すこと、つまり現代賃金労働者(サラリーマン)と生産手段との「再結合」を果たすことである。これは、いわば賃金労働者と農民という近代と前近代のこの二つの人格的融合による歴史的回帰と止揚(レボリューション)、すなわち21世紀の新たなる人間の社会的生存形態の創出を意味している。これによって、相対的に自給自足度が高く、市場原理に抗する免疫力に優れた「菜園家族」が形成される。それはいまだかつて見ることのなかった、精神性豊かな、慈しみ深い、しかも大地に根ざして生きるおおらかな、素朴で繊細にして強靱な人間の誕生でもある。
新しく生まれてくるこの「菜園家族」を社会の基礎単位に据えることによって、「家族」と「地域」による多重・重層的な協同関係成立の主体的条件が芽生えてくる。それはやがて、土壌学で言う団粒構造のふかふかとした滋味豊かな土を彷彿とさせる、きわめて自然生的(ナチュラル)で人間味溢れる、しかもグローバル市場原理に抗する免疫を備えた自律的な社会構造へと熟成していく。まさにこれは、人間存在を大自然界に包摂する新たな世界認識のもとに、自然の摂理とも言うべき、自然界の生成・進化を貫く「適応・調整」の普遍的原理(本編第十章「今こそパラダイムの転換を」で詳述)に則して、「抗市場免疫の自律世界」を構築していくことなのである。これこそが、今日の市場原理至上主義「拡大経済」社会に対峙する、21世紀における「菜園家族」基調の自然循環型共生社会への道であり、静かなるレボリューションの名にふさわしい、長期にわたる耐える力と英知を内に秘めた本物の変革と言うべきものではないのか。このことなしには、もはやこの国の今日の事態の解決はありえないであろう。
このレボリューションには、長い時間と根気が必要不可欠である。この自覚と覚悟がなければ未来はない。こうした変革への着手を遅らせ先延ばしにすればするほど、事態はますます悪化していく。それだけ解決の道のりは遠のき、困難を極めていく。そうこうしているうちに、恐るべき絶望の淵へと追い込まれ、この国の社会の混迷と世界の構造的矛盾は、いっそう深刻な事態に陥っていくことに気づかなければならない。
アルジェリア人質事件は、大切なもう一つのことを思い起こさせてくれる。圧倒的に強大な権力の圧政、弾圧、暴力に対しては、非暴力・不服従の忍耐強い抵抗運動をもって対峙する。これは、イギリス植民地支配下のマハトマ・ガンジーが苦難に満ちた実践から到達した、実に深くて重い思想である。この思想は、真の解放は暴力によっては決して勝ち取ることができないだけでなく、むしろ暴力によって暴力の連鎖をいっそう拡大させていくという、当時のインドと世界の現実から学びとり導き出された今日にも通ずる貴重な結論でもある。
嘆かわしいことに、今日の世界で起きている事態は、巨額の軍事費を費やし最新の科学技術の粋を凝らしてつくり上げた、政・官・財・軍・学の巨大な国家的暴力機構から繰り出す超大国の恐るべき軍事力と、自己と他者のいのちを犠牲にする方法によってしか、理不尽な抑圧・収奪に対する怒りを表し、解決する術のないところにまで追い詰められている「弱者の暴力」との連鎖なのである。かつてガンジーがインドの多くの民衆とともに「弱者」の側から示した精神の高みからすれば、大国の強大な軍事力すなわち暴力によって「弱者の暴力」を制圧、殲滅し、暴力の連鎖をとどめようとすることが、いかに愚かで恥ずべきことなのかをまず自覚すべきである。「弱者」が窮地に追い込まれ、そうせざるを得なくなる本当の原因が何であるかを突き止め、その原因を根本的になくすことに努力する。これ以外に暴力の連鎖を断ち切る道はない。
結局、それを突き詰めていけば、先にも述べたように、先進資本主義国私たち自身の他者を省みない利己的で放漫な生活のあり方、それを是とする社会経済のあり方そのものに行き着くことになるであろう。暴力の連鎖がますます大がかりに、しかも熾烈を極め、際限なく拡大していく今日の状況にあって、超大国をはじめ先進資本主義国の深い内省と、そこから生まれる寛容の精神、そして大国自身そのものの変革が何よりも今、求められている所以である。
ガンジーはイギリス資本主義の植民地支配と闘う中で、真の独立・自治(スワラージ)は単なる権力の移譲ではなく、インド再生の鍵は農村にあるとし、個人の自立と民族の独立の象徴として紡ぎ車を選び、村落の手仕事の伝統をインド経済の基礎に据え、スワデーシ(地域経済)を復活させようとした。今こそこの深い思想の核心を「弱者」のみならず、むしろ先進資本主義国私たち自身の社会に創造的に生かす時に来ている。
かつて人々は、現実社会の自らの生産と生活の足もとから未来へつながる小さな芽を慈しみ、一つ一つ育み、しかも自らのためには多くを望まず、ただひたすらその小さな可能性を社会の底から忍耐強く静かに積み上げてきた。人間は、このこと自体に生きがいと喜びを感じてきたのである。本来これこそが、生きるということではなかったのか。大地に生きる人間のこの素朴で楽天主義とも思える明るさの中に、明日への希望が見えてくる。これはまさに「静かなるレボリューション」の真髄にほかならない。
旧き世界に訣別し新たなる社会システムを構築するには、それをはるかに超える新たな認識の枠組みが必要になる。今こそ迷いやためらいを断ち切って、18世紀産業革命以来長きにわたって囚われてきた近代の呪縛から、解き放たれなければならない時に来ている。この重大なパラダイムの転換を成し遂げてはじめて、近代を画する新たなる世界、すなわち市場原理に抗する免疫的自律世界、つまり「菜園家族」基調の自然循環型共生社会構築の道は、次第に切り開かれていくであろう。変わらなければならないのは、中東やアフリカやアジアの人々ではない。何よりもまず、先進資本主義国の私たち自身なのである。
21世紀人々は、大地への回帰と人間復活の高度自然社会への壮大な道を歩みはじめる。
あとがき
騙されても騙されても、それでもまた繰り返し騙される。人々はそんな不甲斐なさに打ち拉(ひし)がれ、どうしようもない無力感と政治不信に陥っていく。その一方で、「アベノミクス」なるものの実体のない束の間のつくられた円安・株高に淡い期待を寄せ、浮き足立ち酔い痴れる。さんざんそうさせられた挙句に、またもや「選挙」だと言うのである。何とも不条理で不気味な時代に突き進んでいく。
2012年12月の衆議院選での「一票の格差」訴訟に対して、翌2013年3月に入り、「違憲」そして「無効」の一連の司法判断が次々に下された。思えば、長きにわたって人々を愚弄してきたこの偽りの選挙制度のもとで、私たちは「選挙」だけに頼る「政治」にあまりにも安易に幻想を抱いてきたのではなかったのか。かくも歪曲された「政治」のあり方を民主主義と思い込み、この両者を根本から履き違えてきたのではなかったのか。今こそ覚悟を決め、思考停止と「お任せ民主主義」から抜け出さなければならない時に来ている。
自らの頭で自由に考え、他者を尊重し、ねばり強く対話を重ね、めざすべき21世紀の未来像を共有する。この長期にわたる苦難と試練のプロセスの中からこそ、自らの力量を涵養し、自らの手で、自らの未来を切り開くことができるのである。これこそが民主主義の真髄ではなかったのか。
諦めてはならない。私たちの本当の歴史は、今ここからはじまろうとしている。昌益の精神に学び、「21世紀未来構想草の根シンクタンク自然(じねん)ネットワーク」なるものの必要性とその緊急性を第七章で敢えて喚起したのも、戦後68年が経った今なお、草の根の本物の民主主義が育っていない現状に気づかされたからにほかならない。今日の政治の堕落と社会の混迷の原因のすべてがそこに凝縮されている。本物の民主主義の復権、そして21世紀のあるべき未来像をもとめて止まないひたむきな対話の一角に、ささやかながらも本書が加わることができるならば、こんなうれしいことはない。
長きにわたる閉塞状況から忌まわしい反動の時代へとずるずると急傾斜していく中、それでも怒りを堪(こら)え、じっと耳を澄ませば、新しい時代への鼓動が聞こえてくる。たとえそれが幽かであっても、信じたいと思う。そして対話への期待も、その意義も、未来への光もそこに見出したいのである。
本書をまとめるにあたっては、実に多くの方々からご助言を仰ぐことになった。この場を借りてお礼を申し上げたい。これからはじまる終わりのない長い対話の道のりにあっても、引き続き変わらぬご指導をお願い申し上げる次第である。
最後になったが、昨今の出版界の厳しい情況にもかかわらず、拙稿の真意を瞬時に汲み取り、即座に出版を決断された御茶の水書房の社長橋本盛作さん、そして隅々にまで心を配りご尽力くださった小堺章夫さんはじめ編集部のみなさんにあらためて衷心より感謝の意を記したいと思う。
2013年5月21日 ―小満の日―
琵琶湖畔鈴鹿山中、里山研究庵Nomadにて
閉じる
ご感想・書評など
拙著『グローバル市場原理に抗する 静かなるレボリューション ―自然循環型共生社会への道―』(御茶の水書房、2013年)の書評・紹介・ご感想などは、「ご感想・書評など」コーナー(投稿ページ)に順次、掲載していきます。
わが国の現実と風土に根ざした、私たち自身の21世紀未来社会とはいかなるものなのか、そして、そこへ至るより具体的な変革の道筋とはどのようなものなのか・・・。様々な視点から自由闊達に意見交流がなされ、深められていくことになればと願っています。
★みなさんのご感想も、ぜひ、お手紙やメールで里山研究庵Nomadまでお寄せ下さい。お待ちしています!
ブックレット『森と湖(うみ)を結ぶ 菜園家族 山の学校』

| 題名 | 森と湖(うみ)を結ぶ 菜園家族 山の学校 |
| 著者 | 小貫雅男・伊藤恵子 |
| 発行 | 里山研究庵Nomad |
| 発行年月 | 2009年 |
| 判型・ページ | A5判、106ページ |
| 定価 | 頒価:200円(送料別)ご注文・お問い合わせ先、里山研究庵Nomad |
人々の出会いが、語らいが、21世紀の明日を拓く。
鈴鹿山中・大君ヶ畑集落の休園となった保育園を再活用した「菜園家族 山の学校」を拠点に、森と琵琶湖を結ぶ犬上川・芹川流域地域圏(彦根市・多賀町・甲良町・豊郷町の一市三町)を視野に、自由で自主的な学びあいと地域再生の活動の夢を描く。
本書発行の経緯
年々深刻の度を増している「限界集落」の現状を何とか打開し、次の世代に希望をつなげる新たな活動をスタートさせようと、ここ大君ヶ畑では、2007年の夏以来、「菜園家族 山の学校」の開校にむけて準備を続けてきた。
これは、1999年3月をもって休園となった集落内の旧保育園を再活用し、この地域の自然や歴史を礎に、これまで地元で続けられてきた地道な地域づくりの伝統と経験を活かしながら、21世紀にふさわしい、自然循環型共生の健康で清新な生活と文化の創造をめざすものである。
2009年8月8日に大君ヶ畑で開催された「限界集落サミット」では、「菜園家族 山の学校」がめざす活動や、地域未来の新たな展望を示す「菜園家族」構想の大まかな内容をまとめたこのブックレット『森と湖(うみ)を結ぶ 菜園家族 山の学校』が参加者のみなさんに配布された。
「限界集落サミット」の詳しいご報告は、こちらをご覧ください。
目次
はじめに
プロローグ 私たちはどこから来て、どこへ行こうとしているのか
- 週休五日制の三世代「菜園家族」構想
- いのち輝く「菜園家族」
- 「菜園家族」が育つ場、「菜園家族」を育てる力
- 近江国に21世紀の未来を探る
- おおらかな学びあいの場、温もりある人間の絆
エピローグ はるけき空の彼方に
あとがき
閉じる
『菜園家族21 ―分かちあいの世界へ―』
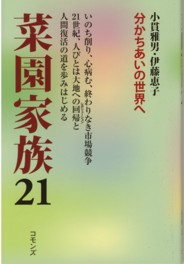
| 題名 | 菜園家族21 ―分かちあいの世界へ― |
| 著者 | 小貫雅男・伊藤恵子 |
| 出版社 | コモンズ |
| 発行年月 | 2008年6月 |
| 判型・ページ | B6判、255ページ |
| 定価 | 本体2,200円+税 |
| ISBN | 9784861870491 |
国破れて山河あり。どっこい菜園家族は生きていく。
容赦なく貶められる人間の尊厳、差し迫る地球環境の破局的危機・・・。市場万能主義に安住していては、地球温暖化は防げない。「菜園家族」構想は、地球の破局を回避し起死回生をはかる、今や私たちに残された唯一の道である。
要旨紹介
国破れて山河あり
どっこい菜園家族は生きていく
投機マネーに翻弄される世界経済。原油・穀物価格の高騰と世界的規模での食料危機。
国内農業を切り捨て、農業・農村を荒廃させ、食料自給率39%に陥った日本。
輸入してまで食べ残すこの不思議な国に、はたして未来はあるのでしょうか。
いのち削り、心病む、終わりなき市場競争
失業者、日雇いや派遣など不安定労働、「ワーキングプア」の増大。
競争と成果主義にかき立てられた過重労働、蔓延する心身の病。
医療・介護・年金など、社会保障制度の破綻。
家族、地域の崩壊、子どもの育つ場の深刻化。
明日をも見出すことができずに、使い捨てにされる若者たち・・・。
貶められても、貶められても、それでも・・・
これほどまでに人間の尊厳が貶められながら、これほどまでに欲しいまま振る舞う「政治」を、これほどまでに長きにわたって許してきた時代も、珍しいのではないでしょうか。
それは、氾濫する雑多な情報に振り回され、ますます肥大化する欲望に翻弄された現代社会の病弊の為せる業なのかも知れません。
今こそパラダイムの転換を
市場競争至上主義のアメリカ型「拡大経済」の弊害と行き詰まりが浮き彫りになった今、18世紀イギリス産業革命以来、二百数十年間、人びとが拘泥してきたものの見方、考え方を支配する認識の枠組み、つまり、既成のパラダイムを根底から変えなければ、どうにもならないところにまで来ています。
大地から引き離され、根なし草となった「現代賃金労働者(サラリーマン)」という人間の存在形態は、果たして永遠不変のものなのでしょうか?
今、あらためて、人類史を自然界の生成・進化の中に位置づけて捉え直し、新たなパラダイムのもとに、未来社会を展望することが求められています。
人間のライフスタイルは変わる
産業革命の到来とともに、人間の暮らしは、中世の循環型社会から大きな変貌を遂げます。新たに登場した資本主義は、不況と恐慌を繰り返し、人びとを失業と貧困の淵に追いやるとともに、他方では、人間の欲望をますます肥大化させ、その渦の中に巻き込んでいきます。
こうした中、人びとは、資本主義の弊害と矛盾を乗り越えようと、新たな社会の枠組みを模索しました。19世紀、人類が到達したこの資本主義超克の未来社会論の核心は、社会的規模での生産手段の共同所有と、これに基づく共同管理・共同運営でした。
20世紀末、ソ連・東欧の「社会主義」体制の崩壊によって、人類の理想への実験は挫折しました。
その欠陥と崩壊の原因がようやく明らかになってきた今、それにかわる道として、生産手段の共同所有ではなく、あえて、生産手段(農地と生産用具・家屋など)と現代賃金労働者との「再結合」が新たに浮上してきます。
この「再結合」を果たすことによって、衰退した「家族」は甦り、この「家族」を基礎に、「自立と共生」の多重・重層的な生き生きとした社会的基盤が築かれます。
つまり、土壌学でいうところの、ミミズや微生物など多様な生き物が共存し、作物がよく育つ、肥沃でふかふかとした団粒構造の土づくりからやりなおし、自然循環型共生社会をめざすのです。
この回帰と止揚の弁証法に基づく未来社会論が、21世紀の新たな道として、必然的に登場してくることになるでしょう。
これが、週休五日制のワークシェアリングによる「菜園家族」(賃金労働者と農夫の二重化された人格)という、人類史上、未だかつて見られなかった、精神性豊かな人間の存在形態の創出であり、これを基調とするCFP複合社会※を経て、自由・平等・友愛の高度自然社会へ至る道なのです。
※CFP複合社会
Cは資本主義セクターC(Capitalism)
Fは家族小経営(「菜園家族」)セクターF(Family)
Pは公共セクターP(Public)である。
森と海(湖)を結ぶ流域地域圏
もとより「菜園家族」は、単独では生きていけません。また、グローバル経済が席捲する今、ひとりでに創出されるものでもありません。
「菜園家族」を育むゆりかごとして、かつて高度経済成長期以前までは、生き生きと息づいていた、循環型の“森と海(湖)を結ぶ流域地域圏(エリア)”を思い起こし、今日の熾烈なグローバル経済の対抗軸として、その地域圏の再生を考えなければなりません。
この本では、近江国(おうみのくに)の一角に、「犬上川・芹川∽鈴鹿山脈」流域地域圏という地域圏モデルを設定し、この個別具体的な一地域圏にこだわり、都市と農村をホリスティック(全一体的)に捉え、深く掘り下げることによって、自然循環型共生社会の構築の普遍につながる理論と、実践の指針を探ろうとしています。
低炭素社会への新たなメカニズムを
今、世界の人びとは、地球温暖化の差し迫る破局的危機に直面し、この危機回避の重い課題を背負わされています。
しかし、地球環境の問題は、「浪費が美徳」の市場万能主義に安住していては、決して解決することはできないでしょう。
「菜園家族」構想は、市場競争に翻弄され、貶められた人間の尊厳を回復し、地球破局の淵から起死回生をはかる、唯一残された道なのです。
本書では、経済成長と地球環境の保全とのジレンマに陥っている、省エネ技術開発やCO2排出量取引制度など、今日の「温暖化対策」の限界を克服すべく、それとは異なる新たな角度から、その解決に迫ろうとしています。
つまり、CO2削減の営為が、ただ単にその削減だけにとどまることなく、同時に、次代のあるべき社会の新しい芽(「菜園家族」)の創出へと自動的に連動する、新たなメカニズムの創設です。
この「CSSKメカニズム」の導入によって、地球温暖化の元凶である市場競争至上主義「拡大経済」は基底部からゆっくりと、しかも着実に変革され、「菜園家族」を基調とする新たな社会、すなわち、自然循環型共生社会への道は、確実に促されていきます。
その結果として、今日、IPCCなどで提起されている、「2050年までにCO2排出量を半減する」という国際公約も、現実に果たされることになるでしょう。
こうして、自然との融和を基調とする分かちあいの世界へと、道は開かれていくのです。
おおらかな学びあいの場と温もりある人間の絆を
「教育」の現場が、「研究」の現場が、そして社会が閉塞状況に陥り、生気を失っている今、戦後の焦土の中から芽生えたあの“めだかの学校”の生き生きとした、自由で平等で友愛に満ちた精神は、目にまばゆいまでに新鮮です。
私たちは、このいのち輝くみずみずしい精神を、子どももおとなも世代を超えて、もう一度、何とか取り戻したいと願うのです。
自然循環型共生社会への道も、こうした願いを叶える小さな努力から、その第一歩がはじまるのだと思います。
その具体的な取り組みとして、琵琶湖に注ぐ犬上川・芹川流域の最奥の過疎山村・大君ヶ畑(おじがはた)では、この森の集落に佇む今は休園となった小さな保育園を拠点に、「研究」・「教育」・「交流」を全一体的に捉えた新しい学びあいの場、「菜園家族 山の学校」のスタートに向けて、動きはじめようとしています。
21世紀、人びとは、素朴な精神世界への回帰と
人間復活の壮大な道を歩めはじめるのです。
目次
プロローグ 国破れて山河あり
第1章「辺境」からの視点
- モンゴル『四季・遊牧』から「菜園家族」構想へ
- 森と琵琶湖を結ぶ十一の流域地域圏
- 里山研究庵と調査活動の進展
- “菜園家族 山の学校”から広がる展望
第2章 人間復活の「菜園家族」構想
- 「菜園家族」構想の理念と原理
- 民話『幸助とお花』の世界
- 蔑ろにされた先人の思い、分断された流域循環
- 大地を失い、衰退する家族 ―「競争」の果てに
- 家族と地域再生の基本原理 ―生産手段との再結合
- 「菜園家族」構想とCFP複合社会
- 週休五日制の三世代「菜園家族」構想
- CFP複合社会の創出 ―人類史上、はじめての挑戦
- CFP複合社会の特質
- 二一世紀の新しい地域協同組織「なりわいとも」
- 自然の摂理と「菜園家族」
- 自然界を貫く「適応・調整」原理
- 自然法則の現れとしての生命
- 自然界の原理に適った週休五日制のワークシェアリング
- 二一世紀“高度自然社会”への道
- 地球温暖化と「菜園家族」
- 早急に求められる地球温暖化への対応
- 日本の取り組みの限界
- もはや元凶の変革は避けては通れない
- 「菜園家族」の創出は地球温暖化を食い止める究極の鍵
- 子どもや孫たちの未来を見据えて
- 日本の、そして世界のすべての人びとが心に秘める終生の悲願
- 「環境先進社会」に学ぶ
- 排出量取引制度を超える方法を探る
- 低炭素社会へ導く究極のメカニズムCSSK方式
第3章 グローバル経済の対抗軸としての地域
―森と海(湖)を結ぶ流域地域圏再生への道
- 中規模専業農家と「菜園家族」による田園地帯の再生
- 農業規模拡大化路線の限界
- “菜園家族群落”は今日の農政の行き詰まりを打開する
- 「森の菜園家族」による森林地帯の再生
- 荒廃する山の集落と衰退の原因
- かつては賑わった最奥の集落・大君ヶ畑
- 大君ヶ畑の暮らし ―ある老夫婦の半生から
- 「御上」に振り回されて・・・
- 森の再生は「森の民」だけが担う課題ではない
- 森の再生は「森の菜園家族」の創出から
- 「森の菜園家族」の具体的イメージ ―森の多様性を取り込み、木を活かす
- 「森の菜園家族」の「なりわいとも」
- 山の活用に斬新な発想を ―尾根づたい高原牧場ベルトライン
- 伊那谷の家族経営牧場に学ぶ
- 集落衰退に拍車をかけた分校の統廃合
- 地域における学校の役割
- 二一世紀、都市から森への逆流が始まる
- 「匠商(しょうしょう)家族」が担う中心街と中核都市
- 非農業基盤の零細家族経営と中小企業
- 「匠商家族」とその「なりわいとも」
- 「匠商家族のなりわいとも」の歴史的使命
- 犬上川・芹川流域地域圏における「匠商家族」と、その「なりわいとも」
第4章 地域再生に果たす国と地方自治体の役割
- 公的「土地バンク」の設立 ―農地と勤め口(ワーク)のシェアリング
- 「菜園家族」のための住宅政策 ―戦後ドイツの政策思想に学ぶ
- 新しい地域金融システムと交通システムの確立
- 流域地域圏における地方自治のあり方
第5章 “菜園家族 山の学校” その未来への夢
- “めだかの学校”を取り戻す
- 新しい「地域研究」の創造をめざして ―「在野の学」の先進性
- おおらかな学びあいの場と温もりある人間の絆を
- 諦念に沈む限界集落
- 再起への思い
エピローグ 分かちあいの世界へ
苦難の道を越えて
いのちの思想を現実の世界へ
まことの「自立と共生」をめざして
あとがき
参考文献
閉じる
『菜園家族物語 ―子どもに伝える未来への夢へ―』
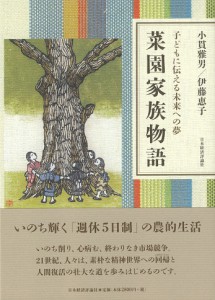
| 題名 | 菜園家族物語 ―子どもに伝える未来への夢― |
| 著者 | 小貫雅男・伊藤恵子 |
| 出版社 | 日本経済評論社 |
| 発行年月 | 2006年11月 |
| 判型・ページ | A5判、373ページ |
| 定価 | 本体2,800円+税 |
| ISBN | 9784818818873 |
子どもたちの小さないのちは、その一つ一つまでもが、実に生き生きと、個性的に輝いている。 むごいことに時代は、不条理の苦しみの世界に小さないのちを追い込んでいく。いのち削り、心病む、終わりなき市場競争。この市場原理至上主義アメリカ型「拡大経済」日本から、いのち輝く「週休5日制」の農的生活への転換を説く。
この本の詳しい内容を見る本書の特長
本書『菜園家族物語 ―子どもに伝える未来への夢―』をまとめるにあたっては、挿絵や版画、歴史的な写真、資料など、図版190点余を織り込み、読みやすく、より理解が深まるよう工夫しました。これら多数の貴重な図版は、画家・研究者・市民活動家・農山村集落のみなさん・ゼミ卒業生・出版社・新聞社等、様々な分野の方々のご協力とご厚意により、掲載させていただくことができました。ややもすると無味乾燥なものに流れがちなこの本に、みずみずしい豊かな視覚的イメージを添えていただきました。
挿絵をご提供くださった水野泰子さん(北海道)、前田秀信さん(長崎県)、志村里士さん(滋賀県)・・・、これら3人の方々の作品に共通していることは、今は過去となった情景に徹しながらも、未来への確かなメッセージが伝わってくることです。それは、すっかり失われてしまった人間のあたたかさを、次代へ甦らせたいという、共通の願いがあるからなのかもしれません。
本書に込められた「子どもに伝える未来への夢」が、読者の方々の胸に多少なりとも息づきはじめることがあるとするならば、これら作品のお陰であると、心より感謝しています。
水野泰子さん、前田秀信さん、志村里士さんの詳しいご紹介は、こちらをご覧ください。
目次
はじめに
第一章 「菜園家族」構想の基礎
- 閉塞の時代―「競争」の果てに
-
「拡大経済」と閉塞状況 市場原理と家族 「虚構の世界」 生きる原型
- 「菜園家族」構想の基礎―週休五日制による
-
三世代「菜園家族」 新しいタイプの「CFP複合社会」 主体性の回復と倫理 「菜園家族」の可能性と展望 予想される困難 家族小経営の生命力
- 甦る菜園家族
-
ふるさと―土の匂い、人の温もり 心が育つ 家族小経営の歴史性
- 「菜園家族」構想と今日的状況
-
危機の中のジレンマ 誤りなき時代認識を 「構想」の可能性と実効性 誰のための、誰による改革なのか グローバリゼーション下の選択 二一世紀の “暮らしのかたち” を求めて
第二章 人間はどこからきて、どこへゆこうとしているのか
- 新しい生産様式の登場
-
道具の発達と人間疎外 市場競争から恐慌へ そして衰退過程へ 一九世紀イギリスにおける恐慌と二一世紀の現代
- 人間復活への新たな思索と実践
-
新しい思想家・実践家の登場 ニューハーモニー実験の光と影 資本主義の進展と新たな理論の登場 人間の歴史を貫く根源的思想
- 一九世紀、思想と理論の到達点
-
マルクスの経済学研究と『資本論』 人類始原の自然状態 自然状態の解体とその論理 資本の論理と世界恐慌
- 一九世紀に到達した未来社会論
-
マルクスの未来社会論 導き出された「共有化論」、その成立条件 今こそ一九世紀理論の総括の上に マルクス「共有化論」、その限界と欠陥
第三章 菜園家族レボリューション ~高度自然社会への道~
- 資本主義を超克する「B型発展の道」
-
生産手段の再結合 「家族」と「地域」の場の統一理論 「B型発展の揺籃期」 「B型発展の本格形成期」 「CFP複合社会」の展開過程
- 人間と家族の視点から
-
個体発生と「家族」 「家族」がもつ根源的な意義 人間が人間であるために
- 自然状態への回帰と止揚
-
生産手段「再結合」の意義 「自然社会」への究極の論理 “流域地域圏社会”の特質―団粒構造 自然界を貫く普遍的原理 「高度に発達した自然社会」へ 今こそ、生産力信仰からの訣別を
第四章 森と海を結ぶ菜園家族
- 日本列島が辿った運命
- 森と海を結ぶ流域循環 森から平野へ移行する暮らしの場 高度経済成長と流域循環 「日本列島改造論」 断ち切られた流域循環 終末期をむかえた「拡大経済」 幻想と未練の果てに 重なる二つの終末期
- 森と海を結ぶ「菜園家族」エリアの形成
-
森はなぜ衰退したのか 流域地域圏構想と市町村合併問題 二一世紀、山が動く 森が甦る契機 地域政策の重要性 国・地方自治体の具体的役割 エリア再生の拠点としての「学校」
- 「家族」と「地域」―共同の世界
-
変化の中の「地域」概念 現存「集落」の歴史的性格 “共同の世界” を支えたもの 身近なことから 「集落」再生の意義
- 菜園家族エリアの構造、その意義
-
「集落」の再生と「なりわいとも」 「菜園家族」と「くみなりわいとも」 基本共同体「村なりわいとも」 森と海を結ぶ「郡なりわいとも」 非農業基盤の「匠商家族」 「匠商家族」と「なりわいとも」 「なりわいとも」とエリア中核都市の展開 「なりわいとも」の歴史的意義
終章 人が大地に生きる限り
- 歴史における人間の主体的実践の役割 自己鍛錬と「地域」変革主体の形成 未踏の思考領域に活路をさぐる 理想を地でゆく
- 文献案内
- あとがきにかえて
閉じる
『森と海を結ぶ菜園家族 ―21世紀の未来社会論―』
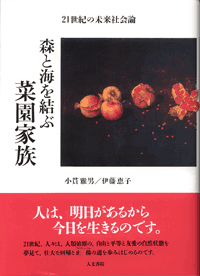
ジャケット装画:柾木 高
| 題名 | 森と海を結ぶ菜園家族 ―21世紀の未来社会論― |
| 著者 | 小貫雅男・伊藤恵子 |
| 出版社 | 人文書院 |
| 発行年月 | 2004年10月 |
| 判型・ページ | A5判、447ページ |
| 定価 | 本体2,200円+税 |
| ISBN | 9784409240700 |
人は、明日があるから、今日を生きるのです。
21世紀、人々は、人類始原の、自由・平等・友愛の自然状態を夢見て、壮大な回帰と止揚の道を歩みはじめるのです。
琵琶湖の東、鈴鹿山中の里山研究庵から展望する犬上川・芹川流域地域(彦根市・多賀町・甲良町・豊郷町の一市三町)。この「森と海(湖)」を結ぶ流域循環型の地域圏モデルを舞台に、未来社会への積極的な方向性を提示する。週の2日は従来型の「お勤め」で賃金収入を確保し、あとは自給自足の家庭菜園に従事するという、21世紀世界の新しいタイプの生き方としてのこの一見大胆奇抜に思える「週休5日制」の「菜園家族」構想に内在する思想は、疲弊しきった現代人に思いもかけない逆転の発想をもたらすことであろう。
目次
はじめに
第一章 「菜園家族」構想の基礎
- 閉塞の時代-「競争」の果てに
-
「拡大経済」と閉塞状況 市場原理と家族 「虚構の世界」 生きる原型
- 「菜園家族」の構想-週休五日制による
-
三世代「菜園家族」 新しいタイプの“CFP複合社会” 「菜園家族」の可能性 主体性の回復と倫理 予想される困難 家族小経営の生命力
- 大地に明日を描く
-
ふるさと-土の匂い、人の温もり 心が育つ 家族小経営の歴史性
第二章 「菜園家族」構想と今日的状況
-
危機の中のジレンマ 誤りなき時代認識を 「構想」の可能性と実効性 誰のための、誰による改革なのか グローバリゼーション下の選択 二一世紀の“暮らしのかたち”を求めて
第三章 「菜園家族」の世界史的位置
- 一九世紀、苦闘と思索の足跡
-
資本の論理と人間疎外 「恐慌」という名の致命傷に向き合う 新しい思想家・社会改革者の登場 オウエン構想の意義と限界 ニューハーモニー実験の光と影 資本主義の進展と新たな理論の登場 一九世紀、思想と理論の到達点 マルクスの経済学研究と『資本論』
- 一九世紀における未来社会論
-
人類始原の自然状態 自然状態解体の論理 資本の論理と恐慌 世界恐慌の不可避性と展望 マルクスの未来社会論 導き出された共有化論 共有化の成立条件 共有化論の欠陥と誤り
第四章 自然社会への道
- 生産手段の「再結合」
-
B型発展の道 「菜園家族」と「地域」 特性としての揺籃期 B型発展の本格形成期 “CFP複合社会”の展開過程
- 人間と家族の視点から
-
個体発生と「家族」 「家族」がもつ根源的な意義 人間が人間であるために 生産手段「再結合」の意義 自然社会への究極の原理 高度に発達した自然社会へ
第五章 日本列島が辿った運命
-
森と海を結ぶ流域循環 森から平野への移行 高度経済成長と流域循環 「日本列島改造論」 断ち切られた流域循環 終末期をむかえた「拡大経済」 幻想と未練の果てに 重なる二つの終末期
第六章 森と海を結ぶ「菜園家族」
- 「菜園家族」と流域循環型地域圏
-
森はなぜ衰退したのか 流域地域圏構想と市町村合併問題 二一世紀、山が動く 森が甦る契機 地域政策の重要性
- 「家族」と「地域」-共同の世界
-
変化の中の「地域」概念 現存「集落」の歴史的性格 “共同の世界”を支えたもの 身近なことから 「集落」再生の意義
- 菜園家族エリアの構造、その意義
-
「集落」の再生と「なりわいとも」 基本共同体「村なりわいとも」 森と海を結ぶ「郡なりわいとも」 非農業基盤の「匠商家族」 「匠商家族」と「なりわいとも」 「なりわいとも」の歴史的意義
第七章 二一世紀、近江国循環型社会の形成
- 森と海を結ぶ流域循環型地域圏モデルの設定
-
湖国近江、滋賀 近江国、十一の流域循環型地域圏モデル aモデル選定の経緯
- aモデル「犬上川・芹川流域循環型地域圏」の昔と今
-
aモデルの地理的範囲 平野部~多賀町の一部と甲良町・豊郷町 平野部~彦根市 山間部~多賀町 雨乞い信仰と流域地域圏 ある老夫婦の半生 民話『幸助とお花』の世界より~循環の思想~
- 地域認識の深化と変革主体
-
作業仮説の設定とその意義 螺旋円環運動と変革主体の形成
- 犬上川・芹川流域循環型地域圏形成の目標と課題
-
流域循環型地域圏構築の基本姿勢 土地利用の視点から-田園地帯- 土地利用の視点から-森林地帯- 森再生の決め手 彦根市街地および三町の中核街 自立的な経済圏成立の前提 国・地方自治体の役割と政策投資
- 近江国循環型社会から世界へ
-
近江国広域圏の一体性 歴史における主体的実践の役割 理想を地でゆく
あとがきにかえて
閉じる
『菜園家族レボリューション』

| 題名 | 菜園家族レボリューション |
| 著者 | 小貫雅男 |
| 出版社 | 社会思想社・現代教養文庫 |
| 発行年月 | 2001年11月 |
| 判型・ページ | 文庫版、208ページ |
| 定価 | 本体560円+税 |
| ISBN | 9784390116459 ※絶版につき、ご注文・お問い合わせは、里山研究庵Nomadまで。 |
市場原理至上主義アメリカ型「拡大経済社会」から、「菜園家族」基調のCFP複合社会へ。巨大化の道の弊害と行き詰まりが浮き彫りになった今、その評価を問いなおし、家族小経営の持つ優れた側面を再考する。
人間を大地から引き離し、虚構の世界へとますます追いやる市場競争至上主義「拡大経済」に、果して未来はあるのだろうか。ここに提起する“大地に生きる”人間復活の唯一残されたこの道に、“菜園家族レボリューション”の思いを込める。
本書の「プロローグ」より
モンゴル遊牧社会の研究をはじめてから、いつのまにか長い歳月が過ぎてしまいました。そ の間、草原や山岳・砂漠の遊牧民家族と共に生活し、一年あるいは二年という長期の住込み 調査や、短期のフィールド調査をまじえながら、日本とモンゴルの間を何回も行き来すること になりました。
ここに提起される日本社会についての未来構想は、この両極を行き来しながら、風土も暮ら しも価値観も、日本とは対極にあるモンゴルから日本を見る視点、そして、そこから生ずる何 とも言いようのない不協和音を絶えず気にしつつ、長年考えてきたことが下敷きになっている のかもしれません。
モンゴルの遊牧民からすれば、日本は「輸入してまで食べ残す不思議な国ニッポン」に映る ことでしょう。本当は憤りさえ覚えているのかもしれません。高飛車に「あんたたちは、経済と いうものを分かっちゃいないんだよね」などと言って、世事に擦れた感覚に、薄汚れた常識を 振り回し、せせら笑ってすませる場合ではないのです。
話は前後しますが、こうした日本とモンゴルの間の長年の行き来の中でも、とくに1992年秋からの一年間、山岳・砂漠の村ツェルゲルでの生活は、日本社会のこの未来構想を考 える上で、貴重な体験になっています。
本書の「あとがき」より
……“菜園家族レボリューション”。これを文字どおりに解釈すれば、菜園家族が主体となる 革命のことを意味しているのかもしれません。しかし、“レボリューション”には、自然と人間界 を貫く、もっと深遠な哲理が秘められているように思えるのです。それは、もともと、旋回であ り、回転でありますが、天体の公転でもあり、季節の循環でもあるのです。そして何よりも、原 点への回帰を想起させるに足る、壮大な動きが感じとれるのです。イエス・キリストにせよ、 ブッダにせよ、わが国近世の希有な思想家安藤昌益にせよ、あるいはルネサンスやフランス 革命にしても、レボリューションの名に値するものは、現状の否定による、原初への回帰の情 熱によって突き動かされたものなのです。現状の否定による、より高次な段階への止揚(アウ フヘーベン)と回帰。それはまさに、「否定の否定」の弁証法なのです。現代工業社会の廃墟 の中から、それ自身の否定によって、田園の牧歌的情景への回帰と人間復活の夢を、こ の“菜園家族レボリューション”に託して、結びにかえたいと思います。
目次
プロローグ
第一章 閉塞の時代―「競争」の果てに
- 「拡大系の社会」と閉塞状況
- 市場原理と家族
- 「虚構の世界」
- 生きる原型
第二章 「菜園家族」の構想―週休五日制による
- 三世代「菜園家族」
- 新しいタイプの“複合社会”
- 「菜園家族」可能性
- 主体性の回復と倫理
- 予想される困難
- 家族小経営の生命力
第三章 大地に明日を描く
- ふるさとー土の匂い、人の温もり
- “心が育つ”
- 理想を地でゆく
- 家族小経営の歴史性
第四章 ふたたび「菜園家族」構想について
- 二十一世紀、人間復活の時代
- 『四季・遊牧』の現代性
- 問題は根深い
- 大地に明日を描く
- 閉鎖からの脱出
- 危機の中のジレンマ
- 誤りなき時代認識を
- 「構想」の可能性と実効性
- 誰のための、誰による改革なのか
- グローバリゼーション下の選択
- 二十一世紀の“暮らしのかたち”を求めて
- 里山研究庵
補章 『四季・遊牧ーツェルゲルの人々』をめぐって
- 『四季・遊牧ーツェルゲルの人々』について
- 作品のあらすじと構成(伊藤恵子)
- 解説ー独自の世界にひたる
- 新しい鑑賞のスタイルの創造をめざして
- “お弁当二つの上映会”
- 『四季・山村ー朽木谷の人々』の制作
- 辺境からの視点
- 異郷の涙
- 究極のアウトドア
- いのちの初夜
- どぜう
- 北国の春
- 早春の賦
エピローグ
文庫版へのあとがき
解説(伊藤恵子)
閉じる
『週休五日制による三世代「菜園家族」酔夢譚』

| 題名 | 週休5日制による 三世代 菜園家族酔夢譚 |
| 著者 | 小貫雅男 |
| 発行 | Nomad |
| 発行年月 | 2000年 |
| 判型・ページ | B5版、89ページ |
| 定価 | 頒価:350円(送料別)ご注文・お問い合わせ先:里山研究庵Nomad |
「大地」から切り離され、「いのち」からますます遠ざかる現代都市型社会に生きる私たち。しかしどうあがいても、この母なる大地から離れては生きていけない。長年のモンゴル遊牧社会のフィールド調査から見えてきた一つの「生きる原型」。そこから提起する21世紀・日本のグランドデザイン。
これまでに寄せられたご感想・書評など
「菜園家族」構想についてこれまでに刊行した拙著に対して、お便りやメールで率直なご感想をいただいたり、新聞・雑誌・Web上に書評や紹介などをいただいたりしてきました。また、この「構想」をめぐる批評や論考も、農業、環境、建築、経済、歴史、思想・哲学等々さまざまな研究分野の方々によって展開されてきました。
それらの中の主なものは、旧サイトの「書評・紹介・論考」コーナーに掲載されています。「菜園家族」構想を多角的に考えていく上で、ご参考にしていただければ幸いです。
小宮山量平先生のご論評から
2012年4月13日、小宮山量平先生は95歳の生涯を静かに閉じられました。
1916年(大正5年)生まれの先生は、戦後の混乱期に大きな志を抱き、早々と出版社「理論社」を興し、思想・論壇界をリード。のちに児童文学に着目、『兎の眼』の灰谷健次郎さんをはじめ、今江祥智さん、倉本聰さんなど多彩な作家を世に送り出してこられました。
そのやさしい目で20世紀の大半を見つめ続けてこられた先生は、、戦後思想史の中にあって、社会・経済・自然科学・技術論・環境・思想・哲学・文化芸術など、広く大きな視野から積極的に発言されてこられました。
晩年には、こよなく愛された郷里の信州・上田に居を構え、自ら作家としても活躍。自伝的長編小説『千曲川』四部作をはじめ、エッセイ集など数々の作品を著し、常に未来への希望を胸に、世を去る寸前まで健筆を振るわれました。
2006年のエッセイ集『地には豊かな種子を』では、「日本民族にとってこれほどの政治的暴力を耐えぬく体験は初めてなのではないか。ガンジーが身をもって示しつづけた少数派の忍耐と楽天主義を、ゆったりと身につける機会が初めて訪れているとも言える」、こうも述べられています。戦後稀に見る人間味溢れる鬼才の編集者といわなければなりません。
今からちょうど10年前の2004年10月、刊行して間もない拙著『森と海を結ぶ菜園家族 ―21世紀の未来社会論―』を先生に献呈したところ、見ず知らずの者であるにもかかわらず、早速、先生から長文のお手紙が届いたのでした。そこには、先生独特のやさしい語り口で、拙著へのご感想とご批評がしたためられていました。その時の感動は、今でも鮮明に脳裏に焼き付けられています。かれこれ10年の歳月が経とうとしていますが、私たちが相変わらず同じテーマを執拗に追究し続けてこれたのも、その時の感動が原動力となっていることを、今あらためて気づかされるのです。
月刊誌『自然と人間』の巻頭エッセイに2005年1月と3月の2回にわたって掲載された、拙著に対する先生のご論評は、今から10年前に書かれたものですが、3・11後のまさに今読み返してみると、その指摘の的確さとその重さをあらためて思い知らされます。初心に立ち返るつもりで、以下に全文を転載させていただくことにしました。
21世紀の未来社会論
― 今こそほんとうの学習運動の燃え上がる季節が訪れている ―小宮山量平(理論社創業者・作家)
あのヒトラーによるファシズムの波が押しよせていたころ、独仏国境にほど近いストラスブール大学の若者たちを励ますかのように謳(うた)われたアラゴンの長い詩の中に、とりわけ心に残る一節がありました。
教えるとは希望を語ること
学ぶとは誠実を胸に刻むこと戦後日本の焼け野原へと帰ってきた若者たちも、こんな一節をつぶやきながら祖国の明日を見つめたものです。今私が机上に開いている一冊の本の冒頭には、ちょうどあのころの敗戦の国土を彷彿とさせるような文章が数多くあって、きりきりと胸が痛みます。
「人々は欲望のおもむくままに功利を貪(むさぼ)り、競い、争い、果てには心を傷つけあい、人を殺し、国家も『正義』の名において、多くのいのちを殺すのです。・・・これほど大がかりに、しかも構造的に人間の尊厳が傷つけられた時代も、ほかになかったのではないでしょうか。」
この本は昨年(2004年)の10月に刊行された一冊なのですが、あたかもあの敗戦直後の祖国を眼(ま)のあたりにしているかのような嘆きを覚えるのです。
なるほど、人によっては第二の敗戦の訪れではなかろうか、と、嘆きを深めないではいられないほどの社会現象が相次いで生じています。とりわけ今ほど人間の労働が軽んじられたことはありません。
「今流行(はやり)のパート、フリーター、派遣労働者。そのどれ一つとっても、これでは使い捨て自由、取り替え自由の機械部品同然ではないでしょうか。これほど人間を侮辱し貶(おとし)めたものもないのです」と、指摘した著者は、あらためて「現代賃金労働者」の問題を根源的にとらえなおそうと迫っています。
私にこの分厚い一冊を送って下さったのは滋賀県立大学人間文化学部の教授・小貫雅男氏で、そのタイトルは『森と海を結ぶ菜園家族』とあり、「21世紀の未来社会論」と副題が添えられ、若き同学の伊藤恵子さんとの共著となっております。お互いにいまだお会いしたこともない私にこのような労作を贈って下さったのは、「『自然と人間』の巻頭言を読ませていただいています」と言うことで、それだけで私には名状し難い同志感が湧いたものです。けれども持ち重(おも)りのするこの一冊のページをめくりながら、ちょうど今200ページ余第四章まで読み進んだ時点で、もはや充分に私の胸は熱くなるのでした。
ああ、こういう本こそが待たれていたのだ!※ ―― と私はつぶやかずにはいられませんでした。ちょうどアコヤ貝がその胎内に異物を容れられる、さぞかし痛みもし不快であろう、排除しようと全身でもだえ、体液を分泌して、その異物を包み込む―と、いつしかその異物を溶かし込んで、円(まろ)やかな乳色の結晶が・・・と、あの美しい真珠の誕生を勝手に空想しながら、私は、今の世の苦しみとの格闘の中から、格別に美しい珠玉の生まれ出ることを期待し、今こそそんな新生の時代が到来すると、待望していたのでした。
まぎれもなくこの一冊は「21世紀の未来社会論」として、こんなにも労働が貶められ、こんなにも正当な権利が踏みにじられ、こんなにも希望の着地点から遠ざけられている若い同胞(とも)たちのために、当代の悩みと苦しみという「異物」との格闘の中から生まれて来たと思うのです。希(ねが)わくはこの一冊を三分冊ほどのハンディなテキスト判として、各地で希望を語り、誠実を胸に刻む学習の環(わ)が生まれたらと夢見るのです。※ あたかも私たちの世代が青年だったころに河上肇先生の第一第二『貧乏物語』にめぐりあった時に感じたようなやさしさと説得力に富んだ本の出現です。
(月刊『自然と人間』2005年1月号 連載巻頭エッセイ「千曲川のほとりで」第27回より転載、発行 自然と人間社)
生命再生産の認識論
― いのちを見つめながら考える新学習運動展開のすすめ ―小宮山量平(理論社創業者・作家)
ありがたいことに米寿を越えたこの老骨を囲んで、フレッシュな学生諸君たちのゼミを企ててくれた大学がありました。一橋大学の就職世話係の先生が、私のような変り種の先輩の話も聞いてみては、と、有志の若者たちに声をかけたのでしょう。男子4名(うち1名は中国人留学生)と女子2名の6名が、東京の私のアトリエに所狭しと集まったのです。以下問答体ふうにその骨子をまとめて紹介したいと思うのです。
小宮山 みなさんを見ていると、まるで私の孫のようで、今やずいぶん酷(ひど)い時代に世に巣立って行かれるものだ、と、心が痛むのです。ふつう卒業しての首途(かどで)であれば、前途洋々の着地を祝い、オメデトウと眼を細めたいところです。けれど21世紀の初頭に入ってから、そういう喜びが急速に失われつつあるのは、どうしたことなのでしょうか?
学生A 確かに私たちの周辺でもメデタイ気分は少なく、できれば留年でもして、もう少し勉強していたいような気分が大いにあります。
小宮山 それというのも諸君を迎える「未来社会」がきわめて不透明で、私どもが「キャプテン・オブ・インダストリー」などと励まされて卒業したような空気は全くない。どんな企業を選んでみたところで、生涯の夢を託するほどの安定性は望めません。この『自然と人間』誌新年号の「21世紀の未来社会論」が語るように、今や人間の労働が極端に軽んじられ、人間の誇りがこんなに貶められている時代はありません。なぜこんな時代を迎えることとなったのかが解明されているはずです。ではどうしたらこの状態から脱出できるのか。この本の著者(小貫雅男教授)たちは、従来の社会変革論の諸説をたどって、その多くをA型発展の道を目指して挫折したものと分類した上で、今こそ大胆にB型発展の道※を目指すべし、と、提唱するのです。
学生B 確かにソ連や中国における社会主義的な実験が、20世紀末に崩壊した現実のショックは、ぼくら世代にも一種のトラウマとして残って、新しい提案には懐疑的です。
小宮山 そうした傷痕を舐(な)めるようにして、世界各国のニューレフトによる反省や批判や修復が試みられているのも事実です。しかし思い切って、敢えて根源的にB型発展の道への探究に踏み切った点で、小貫教授たちによる「森と海を結ぶ菜園国家」の構想は、こんなにも人間の労働が貶められている時代に巣立とうとしている諸君の心に、希望の灯をともすに違いないと思うのです。
学生A そうしたテキストが生まれたことは注目すべきことで、ぼくらもこの本に挑戦してみましょう。
小宮山 そう、その上でもう一度このゼミをやってみましょう。今日は、そんな勉強への弾みとなるようなヒントだけを指摘しておきます。
実はこの正月、日本の主要新聞の多くが挙(こぞ)って少子化問題を最大の危機現象として特集しております。そうした認識の土台には、近未来における国家的な生産力低下への危惧があり、各紙とも社会政策的な知能をしぼっているかに見えます。
けれども今こそ「労働力」は単なる商品ではなく、従来の資本や経営の概念で、その値打ちを左右しうるものではないことを、認識すべき時が訪れている、と、肝銘すべきです。労働力を生命力と置き換えた上で、その「再生産」がどのように祝福されるものとなるのであろうか ―― 小貫教授グループの「菜園家族」という構想には、生命の復活へと私たちの認識を導く光明が潜んでいます。※ ロバート・オーウェン型空想社会主義者からレーニン、スターリン、毛沢東など現実的革命家
すべてが提唱した資本主義から社会主義を経て共産主義へといたる「A型社会観・発展観」に対する、オルタナティブな「発展」観を指す。
(月刊『自然と人間』2005年3月号 連載巻頭エッセイ「千曲川のほとりで」第29回より転載)