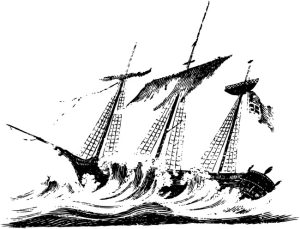長編連載「いのち輝く共生の大地―私たちがめざす未来社会―」第2章
長編連載
いのち輝く共生の大地
―私たちがめざす未来社会―
第一部 生命系の未来社会論、その生成と到達
―自然界と人間社会を貫く生成・進化の普遍的原理を基軸に―
第2章
人間と「家族」、その奇跡の歴史の根源に迫る
◆ こちらからダウンロードできます。
長編連載「いのち輝く共生の大地」
第2章
(PDF:458KB、A4用紙9枚分)
本連載においては、ここまでに触れてきた「労」「農」人格一体融合の人間の新たな社会的生存形態「菜園家族」を基軸に、21世紀社会のあり方を構想していくことになるのであるが、「家族」というものについては、歴史的にも実にさまざまな評価がなされてきた経緯がある。特に近代に入るとその評価はきわめて否定的なものになり、今日に至ってもその傾向は根強く存在している。
一方、まさに“生命系の未来社会論”具現化の道である「菜園家族」社会構想においては、むしろ「家族」がもつ積極的な側面を再評価し、これを地域や社会の基底を成す不可欠の基礎的共同体として、あるべき未来社会の多重・重層的な地域構造を下から形づくり支える大切な役割を担うものと位置づけている。
「菜園家族」を基調とする21世紀の社会構想の具体的な内容に入る前に、まずこの章では、今なぜ「家族」に着目し、それを重視しなければならないのかを明らかにするためにも、「家族」とは本来、人類にとっていかなるものであるのかをあらためて見つめ直すことからはじめたい。
「家族」の評価をめぐる歴史的事情
岸田前首相が打ち出した「異次元の少子化対策」が、この間、国会等でもにわかに取り沙汰されてきた。しかし、根源的視点が抜け落ちたまま議論が進行していると言わざるを得ない。
これまで「家族」については、歴史的に実にさまざまな評価がなされてきた経緯がある。特に今日においては、ジェンダー的視点から「家族」に対する否定的評価が強まる一方、旧統一教会や自民党に典型的な、非科学的で古色蒼然たる家父長的家族観も根強くあり、「家族」をめぐる議論は混迷を極めている。
19世紀前半のロバート・オウエンに代表される、いわゆる空想的社会主義者たちや、その後19世紀のいわゆる科学的社会主義者たちの間でも、「家族」に対する評価はまちまちで、一概に極めて低く、否定的にしか扱われてこなかった。中には、根強い復古的心情から、中世の家父長的家族への回帰を主張する論者もいた。
いずれにしても、未来社会論との関連では、「家族」への考察と評価は十分に深められることはなかったと言えよう。
個々の「家族」の育児・炊事等々の家事労働を社会化すれば、何よりも女性が解放されるとして、家事廃止論にまで行き着く傾向すらあらわれた。当時としては、反封建主義を旗印に掲げる啓蒙的、革新的思想の立場から、むしろ家族の持つ閉鎖性や狭隘性、そして保守的で頑迷な性格の除去、女性の負担軽減、地位向上に最大の関心があったと言えよう。
当時の時代が要請する課題からすれば、そのような主張や議論が起こるのも、ある意味では当然のことなのかも知れない。
こうした時代状況を背景に、19世紀のマルクスやエンゲルスの場合も、未来社会における「家族」の位置づけとその役割については、ほとんど具体的系統的に触れることはなかったし、いわんやそれを未来社会論の中に積極的に位置づけて論ずることはなかったのである。
エンゲルスは晩年、モルガンの『古代社会』に依拠して執筆した古典的名著『家族・私有財産および国家の起源』(1884年)の中で、わざわざモルガンの言葉を引用し、家族の未来について次のように述べている。
「将来において、単婚家族が社会の要求を満たすことができなくなったばあい、そのつぎにあらわれるものがどんな性質のものであるかを、予言することは不可能である。」
この言葉からも分かるように、「家族」への主要な関心は今日とは違い、別なところにあったことだけは確かであろう。特に近代における「家族」についての評価には、こうした歴史的事情や時代的制約があったことをまず念頭においておく必要があろう。
私たちは今、それからおよそ200年もの歳月を隔てた21世紀に生きている。世界を覆い尽くす新自由主義的市場原理至上主義「拡大経済」の凄まじい渦中にあって、あの時代からは想像を絶する事態に遭遇している。
家族の崩壊と「地域」の衰退が進む中で、人と人との絆が失われ、人間が徹底的に分断され、多くの人々が恐るべき「無縁社会」の出現に戸惑い、苦しんでいる。
私たちは、この恐るべき現実を目の前にして、あらためて人間とは、「家族」とは一体何なのかという、この古くて新しい問題に新たな角度から光を当て、考え直すよう迫られている。
未来社会のあるべき姿も、こうした根源からの問いと現実への深い洞察によってはじめて、新たな像を結ぶことが可能になるのではないだろうか。
人間とは、「家族」とは一体何か
ここからは、このテーマに則して、先学たちの代表的な研究成果、時実利彦『人間であること』(岩波新書、1970年)、三木武夫『胎児の世界 ―人類の生命記憶―』(中公新書、1983年)、アドルフ・ポルトマン著、高木正孝訳『人間はどこまで動物か ―新しい人間像のために―』(岩波新書、1961年)等々に依拠して、まずは「家族」とは、人間とは一体何かを自分なりに納得のいく理解をしておきたい。
なかんずくスイスの著名な動物学者ポルトマンは、その著書の中で、ヒトに特有な「常態化した早産」による生まれたての赤ん坊の状態に起因して派生した「長期にわたる『家族』による幼児擁護」が、ヒトに特有の「家族」をもたらしたこと。
そしてその「家族」が、他の動物一般に見られない、異常なまでの脳髄の特異な発達を促す根源的で基底的な役割を果たしていること。
つまり、ヒトを今日の人間たらしめたものは「家族」である、と結論づけている。
一方、アフリカ各地で長年ゴリラの野外研究に専念し、類人猿の生活とその社会的特徴を研究してきた山極寿一氏の『「サル化」する人間社会』(集英社、2014年)、『家族進化論』(東京大学出版会、2012年)でも、人類史における「家族」の根源的な意義について、基本的にはポルトマンと同じ結論に達している。
この両者の結論の一致は、偶然とは言え、一方が野外研究という研究方法上の対称的な側面からのアプローチによる結論であるだけに、時空を隔てながらも巡り合ったこの一致の妙の単なる興味以上に、21世紀の未来社会論を「家族」のもつ根源的意義を重視し、それを基礎に展開してきた立場にある者にとって、何とも心強い証左を得た思いがする。
特異な発達を遂げたヒトの脳髄は、人類の未来にとって“諸刃の剣”とも言える宿命的両義性を持っている。
本連載では、この両義性についても後の章で触れ、「家族」と人間の問題をより深く掘り下げて考察していきたい。
人間の個体発生の過程に生物進化の壮大なドラマが
人間の生涯は、たかだか60年とか70年、長くても80年とか90年に限られた短いものである。この人間の生涯は、卵子と精子の受精によってはじまる。
周知のように、受精卵は子宮壁粘膜に着床すると、子宮内で胎児として発育し続け、十月十日(とつきとおか)の後に産まれる。胎児が母体外に産まれ出ると、胎児と胎盤を結んでいたへその緒(お)は切断され、それと同時に新生児は、呼吸・排泄・摂食などを自分の力でやらなければならなくなる。
しかし、誕生間もない新生児は、まだ自分の力だけで生きていく能力はない。何よりもまず母の授乳を受け、「家族」という厚い庇護のいわば胞膜の中で成長する。やがてことばを覚え、一般の哺乳動物のように四つ足で這うことからはじめ、二足直立歩行へと発達を遂げ、様々な発育段階を経て成人に達する。
この人間の受精卵から成人までの発達過程(個体発生)に注目すると、生物進化の道すじ(系統発生)を推測することができると言われている。これに関連して、ドイツの動物学者ヘッケル(1834~1919)は、「個体発生は、系統発生を繰り返す」という有名なテーゼを残している。
つまり、母体内で胎児として発育を続け、やがて産み出され成人になるまでのわずか十数年の個体発生の過程には、三十数億年前といわれる生命の発生の始原から、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類を経て人類の出現に至る生物進化の過程が凝縮されている、というのである。
生命のふるさとは、三十数億年前の海の中であった。植物と動物が菌類を仲介として向かい合う今日の生態環の基礎が、すでにその時、太古の海を舞台にできあがっていた。そして4億8000万年前の海に、最初の脊椎動物(魚類)が姿をあらわす。
その後、鰓(えら)呼吸と肺呼吸を使い分ける両生類があらわれ、やがて生命発生以来、30億年間の水の生活に別れを告げて、陸の生活に踏み切った脊椎動物が出現する。それが、今から3億年前のデボン紀から石灰紀にかけての時代に、古生代緑地に上陸の第一歩を印した最古の両生類イクチオステガだったのである。この地球の古生代の物語は、「脊椎動物の上陸」と呼びならわされている。
そして、脊椎動物は、その後、両生類から爬虫類へ、さらに鳥類・哺乳類へと分岐しつつ、人類へと進化していった。
この三十数億年という生物進化の壮大なドラマが、現代のこの私たち人間のわずか十数年の個体発生の過程の中に、今でも繰り返されているとは驚くべきことである。人間のいのちの不可思議さと同時に、生命の「深層」の深さと重みをずっしりと感ぜずにはいられない。
母胎の中につくられた絶妙な「自然」
人間の胎児は、母の子宮内の羊膜の中にたたえられた羊水にまもられて、十月十日(とつきとおか)間、ここで成育する。羊水の組成は、古生代海水のそれと酷似していると言われている。「脊椎動物の上陸」が、“海水をともなって”おこなわれたことの紛れもない証拠でもある。
胎児の尿膜の血管は、へその緒を通って胎盤に到達し、母胎の血流と交わる。ここでガス交換と併行して、栄養物の吸収と老廃物の排泄がおこなわれる。したがって、栄養物を蓄える卵黄膜の袋も排泄を助ける尿膜の袋も、本格的に働くことなく、ただ遠い太古の卵生時代の名残りをとどめるだけになっている。これに対して、羊膜の袋は、満々と羊水をたたえている。
つまりこれは、まず、生物進化の道すじである系統発生の原初の生命から、魚類、両生類といった段階の、海の中での最も繊細な進化過程の再現を庇護するかのように、母胎の中にわざわざ「太古の海」を用意していると見ることができる。
そして、出産、つまり胎児が母胎から外に生まれ出て陸地にはじめて「上陸」する時に備えて、胎児と胎盤を結ぶいわば「海中パイプライン」とでもいうべきへその緒を連結することによって、栄養物と老廃物の新陳代謝がおこなわれるようにし、胎児が子宮の中の「太古の海」にいながら、陸上の進化である爬虫類から哺乳類までの発達が遂げられるように保障している。
こうすることによって、胎児が母胎の「海」から陸上に出た時、陸上生活にふさわしい哺乳類として、人体のすべての器官が完備されるまでに発達するように配慮されている。
生命の誕生のために母胎の中に「太古の海」を用意し、人間へのさらなる進化のために「海中パイプライン」まで用意する。神の摂理としか言いようのない絶妙な「自然」が、そこにはつくりだされているのである。
胎児は、十月十日(とつきとおか)、母なる「太古の海」、つまり羊水に浸かって過ごす。胎児は、親指の先ほどの大きさになると、まるで魚のような姿をして、目や耳、それに鰓(えら)までみとめられる。舌の輪郭が定まり、神経もできてきて、感覚も運動も可能になるはずである。
羊水は、胎児の食道から胃袋までを隈なく浸し、さらに肺の袋にも達している。へその緒を介して血液のガス交換が営まれるので、ここではどんな呼吸も必要ではない。胎児のこの「羊水呼吸」は、その後、半年にわたって続けられる。
この間、心臓の発生は、一心房一心室(魚類型)から、二心房一心室(両生類・爬虫類型)へ、さらに二心房二心室(哺乳類型)へと発達を遂げていく。
母胎の中で羊水に浸かった胎児が、その小さな肺で「羊水呼吸」をおこなっている姿は、「太古の海」での鰓呼吸を思わせるものがある。
そして、約10ヵ月後にいよいよ誕生の時をむかえると、狭い産道を通過する間に、肺の中の羊水がしぼり出され、産声とともに外界に出たその瞬間に、「羊水呼吸」にかわって空気による肺呼吸がはじまる。まさにこの「羊水呼吸」は、肺を空気呼吸の機能を備えた器官にまで発達させるためのプロセスであり、トレーニングの過程でもある。
こうして母胎から外に出た胎児は、二度目の「上陸」を敢行したことになる。一度目は、胎内の「太古の海」での、系統発生史上の両生類から陸上爬虫類への転身であり、二度目は、胎児にとってはじめての、母胎の「海」から現実の陸上への進出である。しかも、二度目のこの「上陸」は、哺乳動物としては、二足歩行以前の発達段階での敢行なのである。
他の哺乳動物には見られない、人間に特有な「家族」誕生の契機
薄暗い「太古の海」に別れを告げ、母胎から離れて大地に「上陸」したこの人間の新生児は、高度に発達を遂げた哺乳動物の乳児として、これまでとはまったくちがった想像を絶する世界で成育することになる。
人間が母胎から外に出た誕生時の状態は、哺乳動物の中のさらに霊長類のうちでも例外的な地位を占めている。それは、一種の「生理的な」、つまり「常態化してしまった早産」だと言われている。
このことは、人間の胎児が、高度に発達を遂げた哺乳動物の子供の段階まで母親の子宮の中で育ちきってしまうのではなく、それよりもはるかに早い時期に、未成熟な段階ですでに母の胎内を離れて世に出される、ということを意味している。
一方、人間以外の高等な哺乳類の子は、たいへん発達した筋肉組織と感覚器官をもって生まれてくる。そして、その両者は、神経組織によって脳髄と十全に連動し、機能している。それは、成育した親の姿をそのまま小さくした縮図であり、その運動や行動は、誕生時からほとんど親に酷似している。有蹄類、アザラシやクジラやサルなどがそうで、例えば仔馬などが、生まれ落ちてから数分も経たないうちに自力で歩きはじめようとする情景を思い浮かべれば、よく分かるはずだ。
霊長類の子に限って見ても、誕生時から離巣性をもつものに分類されるべきものである。チンパンジーの子は、生後1ヵ月半も経てば、母親にしがみついて立つことができる。つまり、人間の新生児から見れば、いずれにしても、筋肉組織と感覚器官がはるかに発達を遂げ、この両者が神経組織によって脳髄と十全に連動してから生まれるのである。
こうしたことから、人間の生まれたての赤ん坊のあり方が、どんなに特別な、尋常一様なものでないか、そして他の高等哺乳類にあてはまる法則からは、どんなにかけ離れた存在であるかが納得できるはずである。
人間の胎児は、母胎内で「巣立つもの」の段階へと成育を続け、開かれた感覚器官と完成した筋肉組織を持つ、ある意味では仔馬の段階、つまり、あらゆる哺乳類に特徴的な完成された段階にまで達するのであるが、胎内でこのような長い発達の段階を通りながら、生まれたばかりの新生児は、不思議なことに恐ろしく未成熟でたよりなく「能なし」なのである。
この矛盾は、人間の形成過程が他の哺乳類や霊長類には見られない特別なもので、人間に特有なものであるということを示唆している。
生まれたての人間の新生児の脳髄は、他の高等哺乳類や霊長類に比べて著しく大きく複雑であり、それだけに、成熟に必要な時間が長くなる。とすると、脳髄が発達途上にあり、神経組織によって感覚器官・筋肉組織とも十全に連動していないこの自律不能の期間を、どう解決するかが問題になってくる。
高等哺乳類の段階ならば、それを母の胎内での胎生期間、つまり妊娠期間を長くすれば解決できる。しかし、さらに霊長類、その中でも類人猿と人間のあいだでは、脳髄の発達水準の高さの点で、もう一度かなり飛躍しているところに遭遇する。
そこでもう一度、自活できない依存的な時期をどう乗り越えられるかが、問題になってくる。妊娠期間を再度さらに1ヵ年ほど延長すればいいということにもなるのであるが、ここでは、こうした予想される解決法からはほど遠い、まったく新しい方法がとられたのである。
つまり、妊娠期間の延長による解決ではなく、高等な鳥類の「巣ごもり」の道、すなわち、両親による誕生後の細心のねばり強い養護と注意によって解決する道が選ばれたのである。生まれたての人間は、器官など身体の基本構造から見れば、「巣立つもの」であるけれども、しかし、一種独特な両親への強い依存性を特色とする解決方法が採用されたということになる。
ここに、他の哺乳類には見られない、人間に特有な「家族」誕生の契機がある。
「常態化された早産」、そして「家族」による擁護の道の選択
つまり、脳髄が高度で複雑であることに起因しておこる、人間に特有な「常態化された早産」が、霊長類の中でも例外的な「たよりない能なし」の新生児を胎外に送り出すこと、それゆえに、その子が自立できるまで、長期にわたる「養護」が必要であること、これが、人間に特有な「家族」の発生をもたらしたということなのである。
この「家族」は、母を中核に据えた恒常的で緊密な、ごく小さな血縁的「人間集団」として形成される。
「家族」にこのように特別な方法で依存するのは、哺乳類の中では人間だけである。生まれたてのよく保護されている類人猿の子には、行動や態度や運動、あるいはコミュニケーションの手段において、本質的に新しいものが生じてくる可能性は、もはや与えられていない。
ところが一方、人間では、他の哺乳類であれば、まだ暗い母のおなかの中で、純粋に自然法則のもとで温和に発育を続けなければならないはずのこの時期に、この「子宮外的な時期」を与えられたことによって、突然、社会的・歴史的法則のもとに立たされ、本質的に新しい特殊な発達の可能性がひらかれることになった。
類人猿は、完全な完成形に近い、終局的なこぢんまりした状態に急速に成長するのに対して、人間は、それまでとは比べようもなく多様で複雑で刺激的な子宮外の自然的環境のもとで、「巣ごもり」によって、ゆっくりと時間をかけて成長していく。そして、このことが、人間に特有な「家族」、「言語」、「直立二足歩行」、そして「道具」の発生という、地球の生物進化史上、まったく予期せぬ重大な“出来事”をひきおこすことになったのである。
「家族」がもつ根源的な意義
新生児は、人間形成にとって決定的に大切な誕生以後のほぼ1年間を、母の暗いおなかの中で、自然法則のもとで発育するのではなくて、「常態化した早産」によって外界に生まれ出ることで、多くの刺激のみなもとをもつ大地と自然の中で、同時にはじめは「家族」の中で、そしてやがてより広い社会的環境の中で、まだどのようにでもなる可能性を秘めた素質に、様々な体験を通して刺激を与えられながら過ごすことになる。
この生後第1年の乳児を思い浮かべると、脳髄がいかに指導的な役割を果たしているかにすぐさま気づく。それは、具体的には、動機体系の強さ、直立すること、話すこと、そして世界を体験しようとする努力の強さなどに見られる。
まず、「養護の強化」のために自然にあらわれてくる、母親を中核にした父親・兄・姉・祖父母・おじ・おばなどとの緊密なコミュニケーションの中から、必然的に音声言語が発達し、このことによって、さらに脳髄の発達が促進される。
それがまた人間に特有な「直立二足歩行」を惹起し、さらに両手の自由の獲得によって、「道具」の使用へとすすむ。「言語」、「直立二足歩行」、「道具」の三者が緊密に内的に連動しつつ、「直立二足歩行」をはじめる11~12ヵ月ごろになると、ことばの模倣が盛んになり、脳髄を一層刺激し、新たな発達段階へとすすむ。
「直立二足歩行」、「言語」、「道具」の使用という人間的な特徴が、そもそもはじめからどんなに社会的特徴をもつ現象なのかということが、この状況をつぶさに想像するだけでも明らかになってくる。周囲の人々の助けやそそのかし、励ましと、幼児の側の創造的な能動性と模倣への衝動、この2つの側面は分けがたく相互作用を絶え間なく営みながら、その発達過程を特色づけている。
乏しい本能によって固定された行動様式しかもたない他の哺乳類とはちがって、練習しながら本当に人間的な可能性を成熟させつつ発達する人間のためには、どんなに長い時間がそこには必要であるかが分かってくる。と同時に、個体発生の様々な発達事象との密接な連関によって、一人の人間の発達がはじめて成立することも理解できる。
「家族」がヒトを人間にした
こう見てくると、人間に特有な「常態化された早産」に起因して派生した「長期にわたる養護」が、人間に特有な「家族」をもたらすこと、そしてその「家族」が、人間発達にとっていかに根源的で基底的な役割を果たしているのか、その重大さに気づくのである。
しかも、人間の場合、どの哺乳動物よりも、どの霊長類よりも、その発達は緩慢であり、長期にわたっている。性的成熟の時期、つまり生殖可能な状態に到達する時期が、他の哺乳類のウシの場合であれば、誕生から1年半ないし2年、ウマが3~4年、サルが4~5年、チンパンジーでも8~10年であるのに対して、人間は13~15年といわれている。他の哺乳類や霊長類に比べて、人間の性はいかに成熟が遅く、したがって、世代交代までの期間がいかに長いかが分かる。
このように、人間の「家族」が極めて長期にわたって安定的であることを考えあわせると、人間にとって「家族」というものが、人間発達の不可欠の場として、他の動物の場合よりもいかに大きな意義を有しているかが、一層はっきりしてくる。
以上のように考察してくると、「家族」、「言語」、「直立二足歩行」、「道具」という4つの人間の発達事象は、相互に深く密接に作用し合うものでありながらも、なかんずく「家族」は、他の3つの事象の根っこにあって、それらの発達を支える基盤を形成しつつ、それ自身の役割をも同時に果たしていることが分かってくる。
つまり、「家族」は、4つの人間の発達事象の中でも、ヒトが人間になるための最も基底的な役割を果たしてきたと推論できるのである。
しかも、受精卵から成人に達するまでの個体発生が、「直立二足歩行」が可能になり石器をも使用する最古の人類があらわれた二百数十万年前から今日に至るまで、永続的に繰り返されてきたことを思う時、「家族」は、「常態化された早産」が発生したその時から今日まで、人間が人間であるために、必要不可欠の役割を演じ続けてきたといわなければならない。
「家族」がヒトを人間にしたのである。そして、「家族」がなくなった時、人間は人間ではなくなるのである。
◆「いのち輝く共生の大地」第2章の引用・参考文献◆
J・S・ミル『女性の解放』岩波文庫、1977年
ベーベル『婦人論』(上)(下)岩波文庫、1981年
水田珠枝『女性解放思想の歩み』岩波新書、2000年
エンゲルス『家族、私有財産および国家の起源』国民文庫、1989年
アドルフ・ポルトマン『人間はどこまで動物か』岩波新書、1961年
時実利彦『人間であること』岩波新書、1970年
三木成夫『胎児の世界』中公新書、1983年
松沢哲郎『進化の隣人ヒトとチンパンジー』岩波新書、2002年
山極寿一『「サル化」する人間社会』集英社、2014年
山極寿一『家族進化論』東京大学出版会、2012年
――― ◇ ◇ ―――
★ 長編連載「いのち輝く共生の大地 ―私たちがめざす未来社会―」の≪ 総目次一覧 ≫は、下記リンクのページをご覧ください。
https://www.satoken-nomad.com/archives/4114
☆ 読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。
2024年10月4日
里山研究庵Nomad
小貫雅男・伊藤恵子
〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地
里山研究庵Nomad
TEL&FAX:0749-47-1920
E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com
(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)
里山研究庵Nomadホームページ
https://www.satoken-nomad.com/
菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページ
https://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/