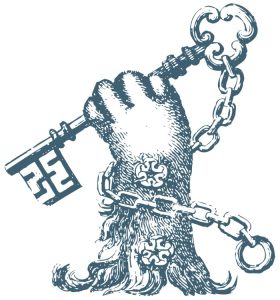長編連載「いのち輝く共生の大地―私たちがめざす未来社会―」第1章(その1)
長編連載
いのち輝く共生の大地
―私たちがめざす未来社会―
第一部 生命系の未来社会論、その生成と到達
―自然界と人間社会を貫く生成・進化の普遍的原理を基軸に―
第1章
生命系の未来社会論、その具現化の道「菜園家族」社会構想の問題意識
(その1)
◆ こちらからダウンロードできます。
長編連載「いのち輝く共生の大地」
第1章(その1)
(PDF:683KB、A4用紙11枚分)
1.21世紀の今、なぜ近代の人間の社会的生存形態「賃金労働者」を問い直すのか
迫り来る世界的危機のまっただ中で ―過剰の中の貧困
投機マネーに翻弄(ほんろう)される世界経済。新型コロナウイルス・パンデミックのさなかにあっても、一握りの巨大金融資本、巨大企業、富裕層にますます莫大な富が集積する一方で、まともな医療さえ受けられず、路頭に迷う圧倒的多数の民衆。
それでもこの機に乗じて、DX(デジタル・トランスフォーメーション)なるものによる新たな成長への幻想を演出しつつ、これまで急速に拡大させてきたにわか仕込みの観光産業※1 と、とどの詰まりはその背後にある巨大金融資本救出のための「Go To トラベル」だの、「Go To イート」だのと、感染拡大防止とは真逆の愚策に1兆数千億円もの国民の血税を注ぎ込む。ここに至ってもなお「浪費が美徳」の経済を煽(あお)る姿に、やるせない思いがつのる。
果てには岸田自民党政権の軍拡大増税に至っては、狂気の沙汰である。ついに、かつての軍国日本の道に一歩踏み込んでしまった。オオタニサン!!などと浮かれている場合ではないのである。
一方、容赦なく迫りくる地球温暖化による異常気象と、世界的規模での食料危機。国内農業を切り捨て、農山村を荒廃させ、食料自給率過去最低の37パーセント(2018年度)に陥った日本。2024年のこの夏には、小売店の店頭で米の品切れが現実に起こりうるのだということを、多くの国民が一瞬ではあるが実感することとなった。
こうした警告をよそに、テレビ画面には相も変わらず大食い競争やグルメ番組が氾濫する。今どき何がそんなにおかしいのか、たわいもないことにおどけ、ニヤニヤ、ゲラゲラ馬鹿騒ぎに浮かれ、四六時中茶の間にまで這入りこんでくる。
現実世界とのあまりにも大きな落差に戸惑いながらも、一体これは何なのだ、と首をかしげるばかりである。これでは、不条理な現実への無関心、無批判層が増えていくのも当然の結果ではないか。報道倫理をかなぐり捨て、権力迎合のマスメディアの責任は重大だ。
今、失業者、日雇いや派遣、「雇用関係によらない働き方」(個人請負・フリーランス)などの不安定労働、「ワーキングプア」が増大し、所得格差はますます拡大している。非正規雇用は今や雇用労働者のほぼ40%に達し、特に若者世代では半数にもおよぶと言われている。正社員であっても、熾烈なグローバル市場経済の渦中にあって、もはや安泰とは言えない不安に苛(さいな)まれている。
一方、福祉・年金・医療・介護など、庶民の最後の砦ともいうべき社会保障制度は、機能不全に陥り、破綻寸前にある。2022年10月1日から、75歳以上の後期高齢者の医療費窓口負担金の割合は、1割から2倍の2割に引き上げられた。この改悪の狙いは、いずれ遠からず全世代にまで及んでくる。
競争と成果主義にかき立てられた過重労働、広がる心身の病。弱肉強食の波に呑まれ、倒産に追い込まれる弱小企業や自営業。ひとたび事が起これば、真っ先に解雇される非正規・不安定労働者たち。明日をも見出すことができずに、使い捨てにされる若者たちの群像。
1998~2011年まで14年連続年間3万人を超えていたものの、近年減少傾向が見られた自殺者数が、コロナ災禍の中で女性・若者を中心に再び増加に転じている痛ましい現実。家族や地域は崩壊し、子どもの育つ場の劣化が急速にすすみ、DV(ドメスティック・バイオレンス)や児童虐待が社会問題化している。
学校給食でしか、まともな食事が摂れない子どもたち。フード・バンクや子ども食堂などの活動に支えられ、何とか凌いでいるシングル・マザーたち。もう忘れてしまったのであろうか、コロナ災禍の際、親の収入が減った上、アルバイトもなくなり、従来の授業料に加え、遠隔授業に対応するための新たな自己負担が増し、食料配布支援に列をなした学生たち。
一方、政財界肝煎りで強行された「Go To トラベル」事業で、食べきれないほどの豪華料理のサービスで集客を競う高級ホテルや旅館、普段は宿泊できないような高額なホテルに予約が集まるというまことに贅沢な消費行動を連日のように報道したマスメディア。
このまったく相反するちぐはぐな二つの情景が同時に並存していること、そして何より、「そうしないと経済が回らない」というマジック・ワードの魔法にかけられ、こうした不条理に対して、もはや疑問や憤りを覚えることすらないほど感覚が麻痺してしまった多くの一般市民のありようそのものが、格差と分断が常態化した今日の日本社会の紛れもない現実を象徴している。
どれひとつとっても、私たちの社会のありようそのものが、もはや限界に達していることを告発している。
いのち削り、心病む、終わりなき市場競争
あれからもう何年経ったであろうか。「働き過ぎ社会に警鐘」という見出しで、いわゆる過労自殺をめぐり、最高裁が企業の責任を認めたはじめての判決が大きく報じられていた。
「まじめで責任感が強く、きちょうめんで完ぺき主義」と評価された青年が、なぜ自ら命を絶つ道を選ばなければならなかったのか。二審判決は、こうした性格ゆえに仕事をやりすぎたとして、死の責任の一端を青年本人に求めたが、この日の最高裁の判決は、安易な過失相殺で個人に責任を転嫁することは許されない、とする姿勢を明確に示した。
どんなにモノが溢れていても、人間が人間らしく生きることができなければ、何の意味もない。人間が巨大な機械の優秀な一部品となって、どんなにモノを効率よく大量につくり出し、身のまわりにどんなにモノを溢れるようにしたところで、この部品は所詮人間ではなく、ただの部品にすぎないのである。
私たち現代人は、人間性を根こそぎ奪われ、ついには巨大な機械の一部品にされてしまった。使いに使われ、さんざんな目にあって摩耗し、ついには役に立たなくなったら捨てられてしまう。
過労死・過労自殺とともに、最近、不眠やうつ症状に悩む人が急増し、大きな社会問題になっている。多くの人々が苦しみ、長いトンネルから抜け出す方法を必死で探しているこうした心の病。
その多くは結局、個人の心の持ち方のみで解決できるようなものではなく、人間の存在をあまりにも簡単に否定し、生きるための経済的基盤を奪い取り、人間の尊厳をズタズタに傷つけて憚らない、徹底した効率主義・成果主義の無慈悲な思想が働く現場の人々の心の奥底にまで浸み入り、精神を追いつめていることが根本にある原因なのではないだろうか。
毎日、働いて働いて、ちょっとだけ休みたくても、そんなことをしようものなら、成果主義の競争の中では、誰かに先を行かれて、即、首を切られてしまうのではないか。そうなったら、この過剰雇用の時代、もう二度と職を得ることができないかもしれない・・・・・・。体力そのものの限界と、そんな恐怖と不安のはざまでどうにもならなくなり、ついには心を病んでいく。
こんな心を病む社会が、人類のめざす発展した社会、豊かな社会だったのであろうか。生産性が多少とも下がろうと、モノが多少、少なくなろうとも、大切なことは、人間が生き生きと暮らせる、心が育つ社会でなければならないということなのではないか。
今では忘れられた、現代のあまりにも凄惨なある事件から考える
今からおよそ21年前の2003年9月16日ことであった。昼休みをしていた午後1時すぎ、テレビの画面に突然、ニュースが飛び込んできた。
激しい爆音とともにビルの窓から炎が噴き出し、間もなく激しい黒煙が上がった。場所は、名古屋市東区のオフィスビルで、刃物を持った男性がガソリンのようなものをまき、人質を取って立てこもったこの事件は、発生から約3時間後に、その男性を含む3人が死亡、40人以上が負傷する惨事となった。
21年前の過去のあまりにも凄惨なこの事件を、ここで今敢えて取り上げるのはなぜか。
順風にのり、経済成長たけなわの一時期、現代資本主義の本性はすっかり影を潜めたかのように見えていた。しかし、21世紀に入ってまもなく起きたこの事件をもう一度生々しく思い起こし、その背景を垣間見る時、近代初期資本主義の粗暴で露骨な搾取とは違い、真綿で人の首を絞めるような陰湿、狡猾な手口で現代賃金労働者を苦しめ、貧困のスパイラルへと追い遣っていく仕組みが、現代日本社会の隅々にまで頑強に張りめぐらされていることにあらためて驚かされる。
そして、現代資本主義が表面ではすっかり変わったかのように見えながら、実はその本質は近代初期資本主義以来、一向に変わっていなかったどころか、むしろより巧妙かつ大がかりに、社会を、そして地域を根こそぎ衰退させ、果てには人間の精神をもとことん蝕み、社会を混迷の深い闇に落とし入れていることに気づかされるのである。
さて、この男性は、立てこもった後、そこにいた支店長に軽急便の本社に電話をかけさせ、「7、8、9月の未払い分の給与25万円を振り込め」と委託運送代金の振り込みを要求。同社によると、契約料は2ヵ月後に支払う約束で、男性には7月分を9月19日に支払う予定だったという。
黒煙とともに窓ガラスや書類が飛び散ったあの光景は、今でも鮮明に脳裡に焼きついて離れない。
新聞報道によると、押し入って死亡したこの男性(当時52歳)は、中学校を卒業、建具会社に15年間勤めた後、運送会社など4社を転々としていた。その後、食品会社では配達業務を担当。同僚の社員は、「仕事はきっちりまじめだった」と話している。前に勤めていた運送会社の社長(当時51歳)も、「無断欠勤ゼロで有休もほとんど消化せず、まじめ一筋」と評している。近所の方は、事件の1年ほど前、この男性の妻から、「貯金を食いつぶしたから、私もパートで働く」と聞いたという。
事件の数ヵ月前に、この男性は軽急便の会社と委託契約を交わし、経費込みで約105万円の配達用バンを購入。頭金60万円を払い、残り45万円を60回払いで返済している途中だった。実際には事件のあった年の3月末ごろから働き始め、6月までに支払われた委託運送料は月平均10万円程度、周囲の人には給料が安いと愚痴をこぼしていたという。
高校生の娘さんと息子さんと妻の四人暮らし。名古屋という大都会のただ中で、この収入では一家4人がとても生活できるものではなかった。困り果てたこの男性は、早朝に新聞配達もはじめたという。
少しでもましな別の仕事口があったとしても、今の会社に借金で縛られている身では、職を変えようにも変えられない。どうにも身動きできない窮地に追い込まれた挙句の事件であったようだ。借金返済のためだけに労働を強いられる「債務奴隷」という制度が、経済大国を誇る高度に発達したこの現代の日本社会にもあったことが、白日のもとに晒されたのである。
日本の社会は、一国の首相ともあろう者が、「人生いろいろ、社員もいろいろ」(小泉純一郎首相=当時)などと、そんな呑気なことを言っていられるような状況ではない。
この事件は、たまたま起こった特殊なケースとは思えない。当時急増していたパート、フリーター、派遣労働者。そのどれひとつとっても、これでは使い捨て自由、取り替え自由の機械部品同然ではないか。これほどまでに人間を侮辱し貶めたものもない。完全失業者385万人、フリーター417万人、自殺者年間3万4427人(数字はいずれも2003年事件当時)の現実から、起こるべくして起こった事件であったと言わざるを得ない。
この事件が新聞やテレビで報道されたのは、事件当日を含めてわずか2日間であった。あとは何事もなかったかのように、街の賑わいは日常に戻り、人はそ知らぬ顔でまた急ぎ足に歩きはじめる。茶の間のテレビのチャンネルも、いつものように、何がそんなにおかしいのか、四六時中、つまらぬギャグに空(から)笑いの大騒ぎである。
特に現代の若者の大半は、時給いくらのアルバイトに慣らされながらも、「賃金労働者」という社会的存在については、あまり突き詰めて考えることもないようだ。人類史上、遠い昔から今に至るまで、現在の「働き方」が永遠不変のものとして存在し続け、これから先もいつまでも続くごく当たり前のものとして、何の疑問もなく見過ごされているのだ。
そこへもってこの事件は、あらためて「賃金労働者」という人間の社会的生存形態が、大地から遊離した根なし草のように本質的にいかに脆く不安定なものであり、いかに非人間的で惨めな存在であるかをあらためて気づかせてくれたのである。
「賃金労働者」は、資本主義形成の初期の段階とは違って、高度に発達した現代資本主義の今日では、賃金の格差や職階制による待遇の様々な違いによって、階層分化がすすみ、その内実は単純ではなく、複雑な様相を呈している。したがって、今日、社会の圧倒的多数を占める都会の勤労者を、一口で「賃金労働者」という概念で捉えがたいことも事実である。
しかし、今日の世界経済の構造的変化と行き詰まりの下で、パートや派遣労働者、フリーランサー、ギグワーカーなど不安定労働者の比率がますます増大し、比較的恵まれ安泰であると思われてきた大企業の正社員であっても、雇用条件や勤務形態の変質に伴って、日本国憲法第28条で保障されているはずの勤労者の団結権すら実質上、奪われ、突然のリストラによっていとも簡単に職を奪われてゆく現実に直面すると、「賃金労働者」という概念の本質が、今ほどあからさまな形で露呈した時もないのではないかと実感される。
近年登場し、コロナ災禍を契機に急増した、自転車などで食事宅配代行サービスを行う「個人請負」契約の配達員も、本質的にはこの21年前の軽急便の場合と同様である。
「時間と空間にしばられない自由な働き方」を求める若者や子育て世代の女性などの希望を叶えるかのような触れ込みで、第2次安倍政権下において「働き方改革」の一環として推進されてきたこのような「雇用関係によらない働き方」は、実のところ、ますます労働を不安定化させ、労働者の権利を奪う苛酷な「働かせ方」の蔓延につながるものと言わざるを得ない。
コロナ災禍のどさくさの中で、働く当事者たちの同意なしに、なし崩し的に導入された在宅のテレワークも同様の危険を孕んでいる。2020年7月、新聞の投書欄に、次のような切実な声が寄せられていた。
「・・・わが家でも家族が週2回の在宅勤務。タイムカードはなく、朝食を終わるや、連絡用スマホを片手にパソコンとにらめっこ。時間無制限です。昼食はコンビニ弁当、終日エアコンをつけたリビングで就労しています。会社が家庭に入り込み家族の気遣いも大変。残業代なし。(中略)企業は水道光熱費や通信費、休憩室も食堂も福利厚生も不要。それらはすべて本人持ち。在宅勤務の環境整備のためとして支給される月5千円では済みません。大企業労働者もだんだん“フリーランス”化するような気がします。・・・」(神奈川県・82歳男性)
21年前、今に先駆けて起こった名古屋での軽急便事件は、私たちに極めて強烈な形で、「現代賃金労働者」という人間の社会的生存形態の問題をあらためて歴史を遡って根源的に捉え直すよう迫っている。
二百数十年前の昔、イギリス産業革命によって社会が激動していた時代に、私たちの先人たちが真剣に考え取り組んだように、21世紀初頭の今、私たちは、あらためて人間とは一体何なのか、そして、人類史上、人間はどのような社会的生存形態を辿り、さらに未来へむかってどこへ行こうとしているのか。このことについて、現代社会の圧倒的多数を占めるこの「現代賃金労働者」に焦点を当て、いよいよ真剣に考えなければならなくなってきたのである。
「8050」問題に凝縮され顕在化した日本社会の積年の矛盾
今から5年前、参議院選を直前に控えた2019年6月、与野党論戦の論点に老後の資産形成における「2000万円不足」問題が急浮上してきた。
国民が怒ったのは、政府が言ってきた公的年金の「100年安心」がウソであり、その検証すらすることなく、自分で2000万円を貯めろ、と問題をすり替えたことなのだ。公的年金制度の破綻が、国民の目の前に一気に露呈した形だ。
そんなことはもうとっくに分かっていたことで、この怒りの火にさらなる油を注いだのは、このことを長きにわたって押し隠し、その同じ手口で北朝鮮や中国の脅威を煽り立て、トランプ米大統領(当時)の言いなりに、F35戦闘機や弾道ミサイル迎撃システムなどの購入を次々に決め、莫大な軍事費の浪費を国民に押しつけてきたことではないのか。
さらには、2022年ウクライナ戦争をいい口実に、同年6月29日、岸田文雄首相は、スペイン・マドリードで開幕したNATO(北大西洋条約機構)首脳会合に、日本の首相として初めて出席。日米同盟を新たな高みに引き上げるとともに、日本の防衛力を5年以内に抜本的に強化、その裏付けとなる軍事費の相当な増額を確保する決意だと表明する始末である。
そして、ロシア、中国、北朝鮮の脅威を煽りつつ、周到に準備画策し、2023年3月末の国会において、5年間で43兆円の莫大な軍事予算案を難なく通過させたのである。これが世界に誇る平和憲法を有する国の為政者がやることなのだ。
2019年4月19日、国立社会保障・人口問題研究所が公表した世帯数に関する推計によれば、一人暮らしをする65歳以上の高齢者は、2040年に896万3000人となり、2015年より43.4%増え、全世帯に対する割合は17.7%になるとされている。一人暮らしの高齢者は、家族によるサポートが受けづらいため、介護や日常生活の支援への需要が高まり、国や自治体の財政へのさらなる圧迫につながりかねない。
こうした単身世帯の増加と同時に懸念されるのが、仕事や社会参加せずに孤立する「ひきこもり」である。2019年3月末、内閣府は、40~64歳の中高年ひきこもりが全国に約61万人いるという衝撃的な推計を公表した。
中高年のひきこもりが深刻な社会問題として注目される背景には、バブル崩壊後の1993~2004年頃に大学や高校を卒業し、社会に出た人口規模の大きい就職氷河期世代(1971~74年生まれの団塊ジュニア世代を含む約2000万人。ロストジェネレーションとも呼ばれる)が、今や30代半ば~50代前半にさしかかっていることがある。
長くひきこもる40~50代の子どもを、70~80代の親が支えなければならない、いわゆる「8050」問題。先立つ親の、わが子を思う心情の切なさ、その子自身の将来不安を思う時、それはあまりにも残酷ではないか。今や多くの人々にとって、決して他人事ではなくなっている。
2020年11月に放映されたNHKスペシャル・ドラマ『こもりびと』※2 は、長年ひきこもる40歳の息子と余命わずかな父の葛藤を描く。膨大な取材の蓄積をもとに、現代社会の不条理を人間の内面奥深くからえぐり出し告発した、稀に見る傑作である。
内閣府調査で分かったのは、ひきこもりが子どもや若者のみならず、すべての世代に関わる問題であるということなのだ。
団塊世代(1947~49年生まれ)が75歳以上になる2025年問題は、かねてからよく知られているが、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、65歳以上人口が最も多くなるのは2042年、75歳以上人口のピークは2054年とされている。これは、就職氷河期世代が超高齢社会の主役となる時期と重なる。
雇用の非正規化が進み、無業者が増え、さらに就職氷河期世代の中から老後に生活保護を受けざるをえない人口が増えることにもなれば、追加で必要な給付額は累計20兆円にものぼると言われている。少子化が進む今、このままでは、現行の社会保障制度は財政面からも困難を極め、いずれ遠からず破綻に追い込まれる。
そして忘れてならないことは、近年の政府統計で、雇用労働者の38%超(2152万人、2018年10~12月)を非正規労働者が占め、その75%(1603万人、2017年)が年収200万円未満の極端な低賃金のいわゆるワーキングプアであり、ボーナスの支給は言うまでもなく、何ら身分保障もないまま将来不安に怯えているという現実である。
非正規雇用の女性たちが、正規雇用の労働者との「不合理な格差」の是正を求め、賞与や退職金を支給されないのは違法だと訴えていた2件の裁判で、2020年10月13日に最高裁が下した判決は、こうした多くの人々の切実な願いを打ちのめすものであった。
こうして不安定な非正規雇用で働いてきた人が年金を減らされ、自分で何とかしろと放り出されたら、どんなことになるのか。「8050」問題の悩みの深刻さは、まさにここにある。こんな社会に果たして未来はあるのだろうか。
年金制度の改革をなおざりにして、将来に備えて貯金せよ、投資せよと、当てにもならないその場凌ぎの目先の処方箋を平然と政府が奨めること自体、現実からまったくかけ離れた戯言(たわごと)としか聞こえない。こうした為政者にどんな改革ができるというのであろうか。このまま進んだら、この国の社会はどうなるのか。
就職氷河期世代の親たちの多くは、高度成長期に地方から都市へと出て就職、結婚し、家庭を築いてきた。その子どもたちは、バブル崩壊後、熾烈なグローバル市場競争の渦の中で、規制緩和による雇用の不安定化と、正規、非正規の分断、「自己責任」の風潮に晒され、孤立し、ひとり立ちすくんでいる。
これは自然災害などでは決してない。政治の不作為である。人為による災害というほかない。
この破綻の根源は何なのか。それは、戦後長きにわたってこの社会に澱(おり)のように溜まった強欲資本主義の病弊そのものではないのか。日本が抱え込んだこの積年の社会の歪みは、未来を生きる若者や子どもたちに重くのしかかっていく。
際限なく噴出してくる問題群の一つひとつの対処に振り回されながら、その都度、絆創膏を貼るといった類(たぐい)のその場凌ぎのいわば対症療法は、もはや限界に来ていることを知るべきである。
岸田政権は、こうした国民の切実な問題を放置したまま、ウクライナ戦争や台湾有事などを口実に国民に危機を煽り、莫大な予算額を実に周到具体的に提示し、軍拡大増税を国民に押しつけてくる。
この反国民的本質を覆い隠し、政権浮揚を狙って、「異次元の少子化対策」などと称して、財源の裏付けもないまま、空虚な提案をどさくさ紛れに連呼する。一方、マスメディアでは、大企業の正社員中心の「官製春闘」で満額回答が相次ぐ異例の賃上げムードだと、華々しく喧伝している。そんな政略的魂胆など、土台おかしいのである。
戦後79年、長きにわたって続いてきたこの自民党政権は、国民に背を向け、ついにここまで腐敗しきったのである。それを許してきたのは国民自身でもあり、主権者である私たちこそ、目覚める時ではないだろうか。
今、本当に必要なのは、問題が発生する大本(おおもと)のあり方そのものを変えることである。衰弱し切った今日の病んだ社会の体質そのものを根本から変えていく原因療法に、一刻も早く取りかかることではないか。
それは、少なくとも10年先、20年先、30年先をしっかり見据え、長期展望のもとに、戦後社会の構造的矛盾の克服を人間の社会的生存形態、すなわち根なし草同然となった賃金労働者そのものを根源的に問い直すことからはじめて、足もとの「家族」と「地域」のあるべき姿を見つめ直し、一人ひとりの働き方を根本から変え、地域社会の再生、そしてこの国の社会の再建に粘り強く取り組むことではないのか。
近代の落とし子「賃金労働者」は、果たして人間の永遠不変の社会的生存形態なのか
こうしたことは、わが国だけの問題ではない。グローバル市場原理のもと、過酷な競争経済が世界を席捲して30年近くが経過した今、その歪みが世界各地で噴出している。グローバル多国籍巨大企業や金融資本に莫大な富が集中する一方で、各地の風土に根ざした人々のささやかな暮らしは破壊されていく。
その荒波は、開発途上国のみならず、先進工業国自身の国内産業、庶民の暮らしをも容赦なく侵蝕した。先進国の多くの人々が、従来の延長線上に約束されていたはずの「豊かな暮らし」から滑り落ちていったのである。
その不満と不安から、アメリカ、EU諸国、ロシアをはじめ、世界各地の大衆の間で偏狭な「愛国心」、排他的ナショナリズムが醸成され、これを背景に大衆迎合的な新興政党が台頭し、「強いリーダー」出現の待望と支持が広がりを見せている。2017年1月の「米国第一主義(アメリカ・ファースト)」を掲げるトランプ氏の大統領就任、そして、2024年11月の大統領選での返り咲きに向けて、今なお全米各地で熱狂的支持を集めている現状は、こうした世界的傾向の結末的象徴であるとも言えよう。
今、世界の多くの民衆は、自らの生活基盤を根底から切り崩され、先行きの見えない日々に苛立っている。先進諸国に顕在化している大衆の不満を背景にした排他的志向も、その醜い対立も、その真の原因を突きつめていくならば、結局、今日の耐えがたい閉塞感を根源から打開する新たな未来への指針、つまり、従来の19世紀未来社会論に代わる新たな展望と理論の不在に遠因があることに気づくはずだ。
市場競争至上主義のアメリカ型「拡大経済」の弊害と行き詰まりが浮き彫りになった今、18世紀イギリス産業革命以来、二百数十年間、人々が拘泥してきたものの見方、考え方を支配する認識と思考の枠組み、つまり、近代の既成のパラダイムを根底から変えない限り、どうにもならないところにまで来ている。
大地から引き離され、根なし草同然となった「賃金労働者」という近代の落とし子とも言うべき人間の社会的生存形態は、果たしてこれからも、永遠不変に続くものなのであろうか。 そもそも人間のいのちとは、一体、何だったのであろうか。 今あらためて、人類史を自然界の生成・進化の中に位置づけて捉え直し、新たなパラダイムのもとに、私たちが歩むべき未来社会はどうあるべきかを展望することが求められている。
それが今、私たちに課せられた21世紀最大の課題なのである。
ところで、終戦を青少年期にむかえた世代は、ほとんどの人々がそうだったのであるが、戦後の廃墟と飢えと漠然とした不安の中で、未来へのほのかな希望を胸に、心の奥底から込み上げる何かに突き動かされるように、小・中・高・大学などでの学校教育、あるいは独学に励み、精神的にも何か手応えのあるものを求めて学んできたように思う。
今から思えばそれは、一国にしか通用しないあの偏狭で忌々しい思想の呪縛からの脱却であり、壮大な人類史的視野に立つ世界の普遍的な知の遺産を、戦後日本の歴史学や経済学研究が引き継ごうとしたものであったのかもしれない。
そしてそれらは、学問の世界ではいざ知らず、世間一般、とくに今日の若い世代には、はるか過去のものとして忘れ去られてしまった。しかし、それらを今、あらためて謙虚にここでのテーマに則して振り返ってみると、意外にも新鮮な形で甦ってくるのに気づかされる。
と同時に、今、私たちが生きているこの現代資本主義社会が、あらためて人類史の全過程の中に、首尾一貫した透徹した論理でくっきりと浮かび上がってくるのに気づくのである。そして今、私たちが突き当たっている状況とその課題が何であるのかも、いっそう明瞭になってくる。
古臭いと烙印を押され、洗い流されてしまった数々の理論的諸命題が、イギリス産業革命以来、二百数十年におよぶ人類の苦渋に満ちた数々の闘いと現実の実践的経験を組み込みながら、修羅場にも似た現代の行き詰まった状況の中で、あらためて「否定の否定」として生き生きと活力ある新たな命題に甦り、あらわれてくるのを感じるのである。
それは、旧ソ連邦の崩壊とともに高らかに謳いあげられた資本主義勝利の大合唱が、その後の世界の事態の進展によってまたたく間に色褪せ、しかも18世紀以来、人類が身をもって苦闘し明らかにしてきた資本主義そのものに内在する運動法則が、かえってこの法則自体によって導かれ陥っていく現実によって、皮肉にも検証される結果に終わろうとしていることと無関係ではない。
古いと断罪され烙印を押されたこれらいくつかの諸命題、なかんずく人間の社会的生存形態としての「賃金労働者」という概念は、草の根の新たなる21世紀未来社会論、つまり“生命系の未来社会論”構築の決定的な鍵になっている。
この「賃金労働者」という人間の社会的生存形態は、18世紀イギリス産業革命を起点とする近代初期資本主義から、今私たちが生きている21世紀初頭の現代資本主義に至る二百数十年の歩みを辿りつつ、それぞれの時代の特徴や特質、それにその時々に浮上してきた問題や未解決のまま残された課題などを整理・検証する時、その歴史的性格とその脆弱性・不安定性、そして何よりも非人道性がより明確になってくる。
こうすることによって、「労」「農」人格一体融合の抗市場免疫に優れた新たな人間の社会的生存形態「菜園家族」※3 と、それを基盤に成立するCFP(Capitalism・Family・Public)複合社会※4 が、はるか彼方にめざす高次自然社会※5 に至る人類史の長いスパンの中で、どんな歴史的位置を占め、そしてその果たすべき歴史的役割が何なのかが、はっきりしてくるにちがいない。
※1 にわか仕込みの観光産業の真相とその本質については、本連載の第10章「気候変動とパンデミックの時代を生きる ―避けては通れない社会システムの根源的大転換―」の7節「パンデミックによって露わになったこの国社会の構造的矛盾」で後述。
※2 NHKスペシャル・ドラマ『こもりびと』NHK総合テレビ、2020年11月22日放送。作 羽原大介、演出 梶原登城、取材 森田智子・宮川俊武。
※3 本連載の第6章「『菜園家族』社会構想の基礎 ―革新的『地域生態学』の理念と方法に基づく―」で後述。
※4 資本主義セクターCと、家族小経営セクターFと、公共的セクターPの3つのセクターから成る複合社会。本連載の第6章で後述。
※5 本連載のエピローグ「高次自然社会への道」で後述。
◆「いのち輝く共生の大地」第1章(その1)の引用・参考文献(一部映像作品を含む)◆
川人博『過労自殺』岩波新書、1998年
宮本みち子『若者が<社会的弱者>に転落する』洋泉社新書、2002年
森岡孝二『働きすぎの時代』岩波新書、2005五年
NHKスペシャル・ワーキングプア取材班 編『ワーキングプア ―日本を蝕(むしば)む病―』ポプラ社、2007年
湯浅誠『反貧困 ―「すべり台社会」からの脱出』岩波新書、2008年
今野晴貴『ブラック企業 ―日本を食いつぶす妖怪』文春新書、2012年
森岡孝二『過労死は何を告発しているか ―現代日本の企業と労働』岩波現代文庫、2013年
森岡孝二『雇用身分社会』岩波新書、2015年
「特集『シェア・エコノミー』とは何か」、『経済』2018年9月号、新日本出版社
脇田滋 編著『ディスガイズド・エンプロイメント ―名ばかり個人事業主』学習の友社、2020年
高田好章「デジタル社会における働き方の現実 ―スマホと自転車」『経済』2020年12月号、「特集『デジタル社会』実像と課題」、新日本出版社
NHKスペシャル『コロナ危機 女性にいま何が』NHK総合テレビ、2020年12月5日放送
牧野富夫「コロナ危機下のテレワーク・『ジョブ型雇用』」『経済』2021年1月号、新日本出版社
国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2019年推計)、2019年4月19日、国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
内閣府『生活状況に関する調査報告書』(平成30年度)、2019年3月、内閣府ホームページ
藤本文朗「『社会的ひきこもり対応基本法』をさぐる」『日本の科学者』2020年11月号、「特集 高齢者の社会的孤立と生涯発達」、日本科学者会議
NHKスペシャル・ドラマ『こもりびと』作 羽原大介、演出 梶原登城、取材 森田智子・宮川俊武、NHK総合テレビ、2020年11月22日放送
NHKスペシャル『ある、ひきこもりの死 扉の向こうの家族』NHK総合テレビ、2020年11月29日放送
堤未果『ルポ 貧困大国アメリカ』岩波新書、2008年
堤未果『ルポ 貧困大国アメリカⅡ』岩波新書、2010年
――― ◇ ◇ ―――
★ 長編連載「いのち輝く共生の大地 ―私たちがめざす未来社会―」の≪ 総目次一覧 ≫は、下記リンクのページをご覧ください。
https://www.satoken-nomad.com/archives/4114
☆ 読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。
2024年9月13日
里山研究庵Nomad
小貫雅男・伊藤恵子
〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地
里山研究庵Nomad
TEL&FAX:0749-47-1920
E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com
(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)
里山研究庵Nomadホームページ
https://www.satoken-nomad.com/
菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページ
https://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/