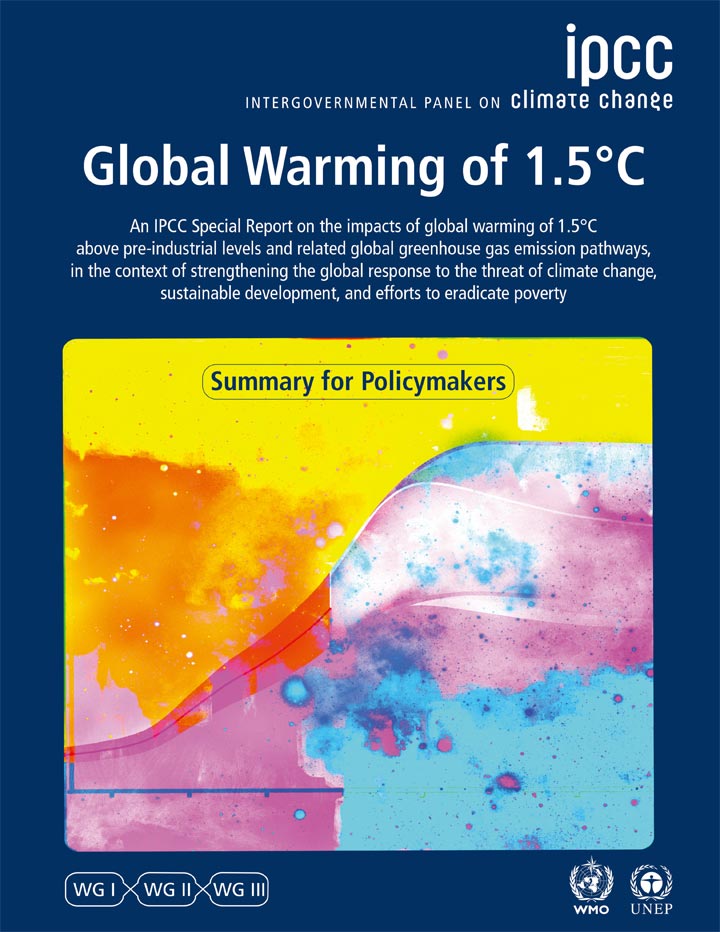連載「気候変動とパンデミックの時代を生きる」≪その2≫
2021年11月17日に、菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページhttps://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/に掲載した、連載「気候変動とパンデミックの時代を生きる」≪その2≫を、以下に転載します。
なお、新プロジェクト“菜園家族じねんネットワーク日本列島”の趣意書(全文)― 投稿要領などを含む ― は、こちらをご覧ください。
【連載】気候変動とパンデミックの時代を生きる ≪その2≫
―避けられない社会システムの転換―
――CO2排出量削減の営為が即、古い社会(資本主義)自体の胎内で次代の新しい芽(「菜園家族」)の創出・育成へと自動的に連動する社会メカニズムの提起――
◆ こちらから全文をダウンロードできます。
気候変動とパンデミックの時代を生きる≪その2≫
(PDF:337KB、A4用紙4枚分)
◆今日までに到達した気候変動に関する世界の科学的知見から◆
今から14年ほど前になりますが、2007年の2月から5月にかけて、世界の科学者の研究成果を結集した「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)第4次評価報告書が公表されました。
「過去半世紀の気温上昇のほとんどが、人為的温室効果ガスの増加による可能性がかなり高い」こと、「平均気温が2~3℃上昇すれば、地球は重大な打撃を受ける」こと、そして、「今すぐ温室効果ガス排出量の削減に取り組み、2015年までに排出を減少方向に転じ、2050年までに半減すれば、地球温暖化の脅威を防ぐことは可能である」ことが、あらためて科学的見地から確認されました。
こうしたIPCCの報告書や科学者の警告に基づき、同2007年12月、第13回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP13)では、2020年までに先進国は、CO2など温室効果ガス排出量を1990年比で25~40%削減するという中期目標と、2050年までに世界全体の排出量を半減するという長期目標が設定されました。
その後、2015年に採択されたパリ協定(2016年発効)では、世界全体の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求することとし、IPCCに対し、1.5℃の地球温暖化による影響と、そこに至る温室効果ガスの排出経路について特別報告書の作成を要請しました。
それまでは、産業革命以前と比べて、2100年の世界の平均気温上昇を2.0℃以内に収めることがめざされていましたが、この1.5℃への重大な目標変更は、2.0℃の目標を達成したとしても、破滅的な社会的・経済的影響が生じ、海面上昇、水不足、生物多様性の喪失、食糧不足などを壊滅的な規模で引き起こすという現実を突きつけられてのことでした。
近年とみに、わが国をはじめ世界各地でスーパー台風、ハリケーンによる豪雨・洪水・浸水などの水害、海面上昇による島嶼住民の壊滅的な被害、オーストラリアでの極度の空気乾燥による大規模森林火災など、これまでの想定をはるかに超える自然災害が頻発し、今や気候変動の危機は、極めて深刻な事態にまで至っています。地球温暖化が広く世界の一般の人々にも、身近な問題として感じられるようになってきました。
気候変動によるこうした差し迫る脅威を背景に、2018年に公表されたIPCC特別報告書『1.5℃の地球温暖化』は、衝撃的とも言える内容になっています。
ここではまず、この特別報告書の要旨を、環境省『IPCC「1.5℃特別報告書」の概要』(2019年7月版)および、肱岡靖明氏の「1.5℃特別報告書のポイントと報告内容が示唆するもの ―気候変動の猛威に対し、国・自治体の“適応能力”強化を―」『地球環境研究センターニュース』(2019年1月号)に依拠し、おさえておきたいと思います。
なお、肱岡氏は、国立環境研究所社会環境システム研究センター地域環境影響評価研究室長を務め、このIPCC特別報告書の執筆に参画しています。
<IPCC特別報告書『1.5℃の地球温暖化』の要旨>
●特別報告書では、産業革命以前の世界の平均気温から1.5℃上昇した場合の影響と、そこに至る温室効果ガスの排出経路を把握し、その評価を行っている。それによると、人為的な活動による世界全体の平均気温の上昇は2017年時点で既に約1.0℃となっており、現在の度合いで温暖化が進行すれば、2030~52年の間に1.5℃に達する可能性が高いとしている。
●人間社会に関しては、1.5℃上昇であっても、健康、生計、食糧安全保障、水供給、経済成長などに対する気候関連リスクが増加し、2℃上昇ではさらにリスクが増加するとしている。一方で、こうした気候関連リスクを低減する適応のオプションが幅広く存在すること、気温上昇を2.0℃ではなく1.5℃に抑えることでほとんどの適応ニーズが少なくなることを高い確信度で示唆している。
こうして特別報告書では、1.5℃がそのような破局を避けるための上限と見なされることになったのです。ところが、このままの排出ペースでいけば、早ければ今から10年後の2030年にも気温上昇が1.5℃に達してしまうというのです。
●特別報告書では、産業革命以前からの気温上昇を1.5℃に抑えるための緩和(温室効果ガス削減)経路について、経済成長や技術の進歩、生活様式などを幅広く想定して導き出している。この中で、1.5℃上昇に抑えるモデル排出経路によっては、二酸化炭素(CO2)排出量を2030年までに2010年比約45%削減、2050年前後には正味ゼロに達する必要があると示唆している。
●世界の平均気温上昇が1.5℃を大きく超えないモデル排出経路では、エネルギー、土地、都市、交通と建物を含むインフラや産業システムでの急速かつ広範囲に及ぶ低炭素化・脱炭素化への移行が必要になるとしている。
●パリ協定のもと、加盟各国はそれぞれ国別目標(温室効果ガス排出削減目標など)を提出している。特別報告書は、すべての国の国別目標を足し合わせた場合の“成果”を見積もっており、現状の国別目標では、たとえ2030年以降の排出削減の規模と目標をさらに引き上げたとしても、1.5℃に抑えることはできないだろう、と述べている。
●さらに、持続可能な開発と貧困撲滅に対する1.5℃上昇のリスクを低減することは、適応と緩和への投資の増加、政策手段の導入、技術革新や行動変容の加速によって可能となるシステムへの移行であることを示唆している。また、持続可能な開発は、1.5℃に抑えることに寄与する社会とシステムへの根源的な移行と変革をサポートすると述べている。
●また、国や地方自治体、市民社会、民間部門、先住民族、地域コミュニティの気候行動の能力を強化することが、温暖化を1.5℃に抑えるという高い目標の達成を支援することになると指摘している。
以上、要旨を見てきたように、特別報告書『1.5℃の地球温暖化』は、1.5℃の上限目標を達成する確率を高めようとするならば、今から10年後の2030年までにCO2など温室効果ガス排出量を45%削減し、今から30年後の2050年までに実質排出ゼロにしなければならないという、まさに一刻の猶予も許されない衝撃的な内容でした。
そして、気温上昇を1.5℃に抑えるためには、新たな社会とシステムへの根源的移行と変革の必要性をも示唆しているのです。
さらに、本年2021年秋には、イギリス・グラスゴーでのCOP26開催直前の10月26日、国連環境計画(UNEP)は、各国が掲げる温室効果ガスの削減目標を達成しても、今世紀末には世界の平均気温が産業革命前から2.7℃上がるとする報告書を公表しました。
先にも述べたように、既に2015年採択のパリ協定では、気温上昇を「2℃よりかなり低く、できれば1.5℃」に抑えなければならないとされており、また、IPCC特別報告書では、気温上昇を2℃に抑えたとしても、熱波や洪水などの影響がきわめて深刻になることが、科学的に示されています。
今回のUNEPの報告は、まさにCOP26直前に、厳しい現実を突きつけた恰好になったのです。
これら一連の報告からも、1.5℃目標達成のために、温室効果ガス排出を2030年までに45%(2010年比)減、2050年までに実質ゼロにするということが、このままでは如何に困難であり、また、地球生態系と私たちの暮らしにもたらされる影響が如何に甚大であるかが、よく分かるはずです。
多岐にわたる専門分野から結集した世界の科学者たち、各界・各分野、そして多くの市民・住民の並々ならぬ努力にもかかわらず、地球温暖化による気候変動が悪化の一途を辿っているのはなぜなのか。今、正念場を迎えています。
先日11月13日に閉幕したグラスゴーCOP26では、気候危機への世界の人々の声の高まりに押され、合意文書に「世界の平均気温の上昇を産業革命前より1.5℃に抑える努力を追求することを決意する」と明記されたものの、参加した各国首脳、とりわけ超大国アメリカと中国、そしてイギリス、フランス、ドイツ、ロシア、日本など大国の首脳の本音は、今日まで世界経済を牽引してきた自動車産業において、EV(電気自動車)化などに伴う脱炭素技術の革新を競う中で、世界市場での新たな主導権をいち早く握るとともに、世界の産業構造を根底から変え、大国間の利害を調整しながら、彼ら共通の利益を何とか確保し、生き延びることにあるのです。
こうした先進諸大国の政治、経済・産業支配層の意図する「グリーン」の背後には、最先端の科学技術によって、市場原理至上主義「拡大経済」システムの再構築をはかろうとする野望が見え隠れしています。
彼らにとって共通にして最大の利益は、飽くまでも先進諸大国支配層に有利な新たな世界経済構造の創出なのであって、「グリーン」はそのための単なる借り物の手段であり、決して目的ではないのです。
まさにそこに、一般市民・住民の素朴な環境意識との大きな乖離と対立が厳然としてあることに刮目しなければなりません。
これでは、さらに大規模で徹底した地球の人工化は避けられず、温暖化を食い止めるどころか、地球生態系の破壊と人間破滅の恐るべき道を辿るほかないのではないでしょうか。
このような人間不在の不遜な経済思想の根源は、一体どこにあるのでしょうか。自然観と社会観の分離を排し、両者合一の普遍的原理に立脚するならば、新たな世界が見えてきます。
それは、ほかでもない、近代にとって宿命的とも言うべき際限のない資本の自己増殖運動そのものにあることが、いよいよ明らかになってくるはずです。
私たちは今、なかんずく18世紀イギリス産業革命以来の資本主義社会のメカニズムそのものを根源的に問い質すことによって、気候変動と社会変革の両者を不可分一体のものとして統一的に捉え、人間復活の具体的で現実的な活路を見出す時に来ているのではないでしょうか。
*『生命系の未来社会論』(小貫雅男・伊藤恵子、御茶の水書房、2021年3月)第七章をベースに再構成。
≪その3≫につづく
(2021.11.17 里山研究庵Nomad 小貫・伊藤)