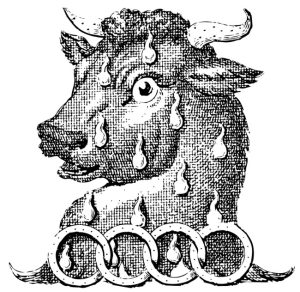長編連載「いのち輝く共生の大地―私たちがめざす未来社会―」第4章
長編連載
いのち輝く共生の大地
―私たちがめざす未来社会―
第二部 生命系の未来社会論の前提
―その方法論の革新のために―
第4章
末期重症の資本主義と機能不全に陥った近代経済学
―21世紀未来社会論のさらなる深化のために―
◆ こちらからダウンロードできます。
長編連載「いのち輝く共生の大地」
第4章
(PDF:612KB、A4用紙10枚分)
近代を超えて新たな地平へ
わが国は2011年3月11日、巨大地震と巨大津波、そして福島第一原発事故という未曾有の複合的苛酷災害に直面した。そして、地球温暖化による気候変動、「数十年に一度の」自然災害が日本列島のどこかで毎年のように頻発する異常気象、2020年新型コロナウイルス・パンデミック、さらには2022年2月24日にはじまるウクライナ戦争。
これら一連の世界的複合危機は、巨大都市集中、エネルギー・資源浪費型の私たちの社会経済の脆さと限界を露呈させた。
この近代文明終焉の分水嶺とも言うべき歴史の一大転換期に立たされた今なお、相も変わらず大方の評者、なかんずく主流派を自認する経済学者やエコノミストは、広く市井の人々を巻き込む形で、従来型の金融・財政上の経済指標や経済運営のあれこれの些細な操作手法に固執、埋没し、目先の利得に一喜一憂する実に狭隘な議論に終始している。
まさにこうした昨今の憂うべき時流にあって、マクロ経済学について門外漢である者としては軽率との誹りは免れようもないが、敢えて本論に入る前に、金子貞吉著『現代不況の実像とマネー経済』(新日本出版社、2013年)などの論考を参照しつつ、自分なりに近代経済学の辿った歴史の展開過程とその性格を見極め、整理しておくことにした。
このことによって同時に、アベノミクスなるものによって煽られた経済政策の淵源とその本質も自ずから明らかになってくるはずである。
この作業を通して、安倍政権を継承すると自認もし、公言もして憚らない菅義偉政権下の「成長戦略」なるもの、そして続く岸田文雄政権の「新しい資本主義」を旗印にした「成長と分配の好循環」なるもの、それを「引き継ぐ」とした石破茂新政権が果たして如何なるものかが、近現代史のグローバルな視野からも明確に位置づけられ、その本質も自ずと明瞭になってくるであろう。
それだけではなく、実は、19世紀未来社会論に対峙し、21世紀の未来社会論を深めていく上でも、それは避けてはならない大切な作業の一つになってくるはずだ。
近代経済学の理論とその手法の特徴は、ごく限られた幾つかの経済指標によって予定される、いわば実体から極端に乖離し矮小化された「経済的虚構」モデルなるものとの照合によってのみ、社会の現実の動向を検証しようとしてきたところにある。この方法では、今日の社会の構造的矛盾の実態をトータルに明らかにすることは不可能であろう。
今もとめられているものは、まさに人間社会そのものの全一体的(ホリスティック)でリアルな「社会的実体」との直接的照合・検証の方法の模索である。
この新たな方法とは、本連載の第5章2節で述べる革新的地域研究としての「地域生態学」が意味するところのものである。この理念と方法によって、21世紀の時代の要請に応えうる未来社会論構築の新たな糸口も見えてくるはずである。その具体的内容とその拠って立つ思想は、本連載の各章で順次、明らかにされていくであろう。
新古典派から抜け出たケインズ理論
20世紀に入っても不況、恐慌は繰り返され、働きたくても雇用がないという事態が相変わらず続いていた。1929年の世界大恐慌を経験したケインズは、マーシャルらケンブリッジ学派(新古典派)の伝統的な経済学では失業の発生は説明できないし、その対策も出てこないと考え、新しい経済理論をつくり上げることになった。
1936年に出版されたケインズの主著『雇用・利子および貨幣の一般理論』は、その中で経済学の「パラダイム」を示した。後にこれが「ケインズ革命」と呼ばれることになるのであるが、経済全体を総量的に捉え、雇用、生産、消費、投資、政府支出、貨幣供給量といった集計された量を変数として、その相互関係、因果関係を考え、モデルを作り、そこからある変数を動かせば、どんな効果が生ずるか、したがって「どんな政策をとればよいか」についての明快なノウハウを示してくれるマクロ経済学を構築したということが、「ケインズ革命」の主な中身になっている。
ケインズはこうしたモデルから、政府が財政支出を増やすことで総需要を拡大する政策が有効だという結論を引き出している。ケインズ理論では、不況は需要不足にあるとみる。不況下では、生産設備や労働力は余っているのだから、供給面ではなく、需要不足に対処しなければならないとする。需要不足という時には、需要は消費財需要と資本財(投資財)需要であるが、投資財不足に主眼をおく。
したがって、需要を増やすのは、投資需要を増やすことである。政府が赤字国債を発行してでも公共事業を起こし、投資財を購入することとしている。そこに雇用が増えて、乗数効果(派生的な需要拡大)が作用して消費も増える。
このように、不況対策として、消費を直接拡大するのではなく、財政出動をもって遊休の投資財を公共事業に使い、フル稼働すればよいとしたのである。
資本主義は、病気になることもある。治療を誤れば、命取りになることもある。1930年代の大不況は、そのことを教えてくれた。人体(経済)のメカニズムについて正しい知識を持ち、その上で治療法を編み出さなければならない。・・・これがケインズの立場であった。
そしてケインズは未来を予測して、「大きな戦争も人口のきわだった増加もなければ、百年以内(筆者註、2030年頃まで)に経済的問題は解決されてしまうか、あるいは少なくとも解決のめどが立っているだろう。このことは、未来のことを考えてみると経済上の問題は人類にとって永遠の問題ではないことを意味している」とも述べている。
これは、あまりにも楽観的に過ぎる見解と言うほかない。ここにも資本主義そのものを永遠不変のものと見ているケインズの歴史観が垣間見られる。
ところでケインズは、新古典派の「貨幣数量説」を脱するために、「流動性選好説」を考え出した。貨幣を「貨幣数量説」のような単に実物経済の流れの仲介役と見るのではなく、実物から離れて動く独自の機能を持つものという新たな知見を加えた。それは債券の売買という債券市場の発達が背景に現れたからである。
ケインズは、「貨幣数量説」から抜け出て、投資は資本の限界効率(投資が将来どれだけの収益を生むかの利益率)と資金調達コストである利子率とが等しくなる水準で決まる、とした。これが新古典派から抜け出した新しい視点であり、ケインズの現実認識の優れた点であると言われている。
20世紀になると株式や債券等の債券市場が発展して、そこで利子率が独自に動いていた背景を直視したからである。過剰資本が形成されて資金が実物投資に回されるだけでなく、債券市場に回り、その市場における資金の需給によって利子率が決まると考えた。
まさにこの安易で手っ取り早い収益の新回路の発達が、今日恐るべき勢いで「経済の金融化」を押し進め、実物経済を撹乱し破綻へと追い込んでいる元凶なのである。
経済の金融化と新自由主義、マネタリズムの登場
1960年、金相場が暴騰し、ドルは事実上暴落する。西欧諸国は金を選好し、アメリカからは金が流出する。アメリカ自体も実体経済が落ち込んで、輸出競争力を失い、貿易収支を赤字化する。こうした経過を辿って、1971年ニクソン大統領が一方的に金・ドル交換の停止に踏み切った。これをきっかけに各国通貨は変動相場制に移行していく。
こうして金融主軸の経済が成立するのは1970年代であるが、貨幣が本来の姿から脱皮して管理通貨となり、信用通貨が膨張する土壌が成立したからである。各国通貨は相対的な価値評価を受けて存立するだけで、信用通貨のこの不安定性が新たに矛盾を生み出すことになる。
国際通貨が変動相場制に転換し、オイルショックに遭い、世界中で景気が後退するのに物価が上昇するという、これまでに見られなかったスタグフレーションに見舞われた。不況なのにインフレーションという相反する2つの要素が同時に起きる未経験の時代である。
戦後の繁栄がこのスタグフレーションによって崩れる中、第2次世界大戦後の安定に役立っていたケインズの有効需要政策に疑問が呈されることになる。ケインズ政策をとる政府の介入は経済の活性化をなくし、物価上昇を招いたとする批判である。
ケインズ経済学にとって代わってアメリカで勢力を得たのが、いずれも同根であるが新自由主義、構造改革派、サプライサイド・エコノミクス、マネタリズム等々である。
新自由主義は、市場原理主義あるいは構造改革派とも言われ、ケインズが否定した新古典派経済学への復帰である。それは政府の経済関与を否定する考え方であり、市場に任せよと「大きな政府」に反対し、自助努力、規制緩和や民営化を主張する考え方である。失業は需要不足にあるとするケインジアンの考え方とは逆に、供給サイドに起因すると考える。新規の経済分野を開拓するために規制緩和をすれば、雇用が増えて経済が復活するという考えである。日本にも1980年代から広がり、民営化、規制緩和が次々実施されてきた。
マネタリズムは、スタグフレーションが発生したのはケインズ主義の失敗であるとみる。政府が不況対策の名のもとに財政肥大化を起こし、通貨膨張になったとみる。そこで、インフレを退治するために通貨の発行量を調節するという方策を採る。その中心人物で、後にノーベル経済学賞を受けたフリードマンが主張した。そのもととなっているのは、古典派経済学の「貨幣数量説」で、その装いを替えて当時の経済的混乱に対処しようとした理論である。
マネタリズムが一挙に広がったのは、当時のアメリカの国内産業が衰え、経済が金融化したことを背景にしている。事実、1970年代半ばからアメリカで新しい金融商品が開発される。長期金利と短期金利の差額から収益をつくり出す金融派生商品(デリバティブ)が広がる。それらはもともとリスク回避策であるが、同時に金融的利益の手段となり、IT技術の発展と組み合わされてアメリカの新たな収益構造をつくり上げてきた。
貨幣が金から切り離されて、信用通貨あるいは管理通貨となったので、貨幣が自由に供給できる仕組みが発達してきた。そういう通貨を自由に発行できる環境で、アベノミクスのブレーンは「貨幣数量説」を復活させて、リフレ派と自称するように、不況は通貨現象であると主張してインフレに持ち込もうとした。
20世紀末になると、世界が金融膨張を続けた結果、金利が低下して、金利操作による経済政策が効果を持たなくなる時代が出現する。1990年頃、ポール・クルーグマンが登場する。彼は「流動性の罠」という状態に日本は陥っているから、そこから抜け出すことがデフレ対策であると主張する。クルーグマンはこの「罠」の視点で日本の長期不況状況を解き明かす。その対策として大々的な金融緩和を提案したので、日本の経済学者やエコノミストに信者が増えて、アベノミクスの論拠となった。
「流動性の罠」とは、利子率が極限までに下がって一定水準以下になり、通貨が滞留する状態を言う。一般には、利子率が低下すると、民間投資や消費が増加すると言われてきたが、極端に低下すると投資の利子率弾力性も低下(投資量が変動しなくなる)してしまい、金融緩和の効果が見られなくなる。利子率がゼロ近辺まで下がり、「流動性の罠」にはまると、金利がそれ以下に低下しないので、人々は低利子に魅力をなくして貨幣のままで保有しようとして、流動性選好がなくなるという。この「罠」に入ると、証券類は収益がないか低すぎるので、貨幣を証券に投資する意欲をなくし、デフレスパイラルから抜け出せなくなると指摘する。
そこでクルーグマンは、名目金利を引き下げることができないのであるから、実質金利を引き下げるしかない。国民に「将来、インフレが起きる」と確信させることができれば、「流動性の罠」から抜け出すことができると主張する。
この提案の原形は、「実質金利=名目利子率-期待物価上昇率」というフィッシャー効果の考えにある。期待インフレ率が上がれば、この式では実質金利を下げることができる。実質金利という現存しない将来値なら、マイナスにすることができるという妙案である。物価上昇率が大きくなれば、確かに実質金利はマイナスになる。要するに、インフレになると誰も思うようになれば、保有する貨幣価値が将来は下がることになるので、貨幣を放出するようになるだろう。貨幣を保有しようという動機が低下し、ものを買うようになるので、デフレを脱することができると考える。
さらにクルーグマンは、実施案として日銀の買いオペを推奨する。「日本銀行が従来とは異なる資産を買い入れるオペを行うことだ。それによって、さらに追加的な流動性(資金)を市場に注入するのである」「日本銀行は外貨や長期国債を買い入れ、インフレターゲットと為替相場のターゲットを設定し、・・・日本銀行が取りうる手段は、すべて取るべき」と言う。2013年の黒田日銀総裁の就任会見も、そっくりの口ぶりであった。
つまり要約すれば、インフレ状態にすれば手持ちの資金が吐き出されて証券投資に向かう。そのために、日銀に積極的に買いオペをさせて通貨を増やし、通貨価値を下げる。そうすればインフレになり、デフレ脱却になると断言している。
クルーグマンは著書『恐慌の罠』(2002年)で「インフレターゲット論」を主張して、日本経済分析の第一人者ということで影響力が大きく、日本に信者が多いと言われている。ただし彼は単純なマネタリストではない。アメリカでの国民健康保険制度の導入に賛成し、失業対策にも積極派である。ケインズ的な財政出動にも賛成派であり、いわゆる「大きな政府」も認めている。そして、こちこちの市場論派とは違って、規制を一定程度認めている。
しかし、日本の現状についてどこまで全体像を掴んでの提案であったか疑問である。2006年まで日銀が量的緩和をしてもデフレ脱却できなかった事実や、アメリカやEUでの金融破綻の実態には直接責任を持つとまでは言えないにしろ、アベノミクスの理論的支柱となれば、日本の事実によって、彼の理論の本質は完膚なきまでに検証されることになるであろう。
暴走するマネー経済と疲弊する実体経済、なかんずく地域社会
今日では金融資産が驚くほど肥大化している。一般に不況過程では実物資産の増加は停滞するのであるが、金融資産は今なお増大している。高度経済成長までは、実物資産と金融資産とは同量の増加傾向をとっていた。それが2011年度では金融資産が約6000兆円に達し、実物資産の約2倍強になっている。ここにも「経済の金融化」が示されている。
21世紀はマネーに狂奔する時代となった。株式、投資信託、不動産投資信託等々、何とも多くの金融商品が出回っている。これらの利益はすべて金融的変動の下で形成される。そして、新たな買い手を登場させなければ、新しい空気を供給しなければ、自らは窒息してしまう。
1990年代は日本のバブル崩壊であり、1997年タイの通貨暴落からはじまるアジアの通貨危機、2007、2008年にアメリカのサブプライムローンを抱えて破綻したリーマン・ショック、2010年ギリシャのカントリーリスクによるEUの金融危機、これらの経済的崩壊現象は、すべて地球規模で「経済の金融化」を極度に押し進めてきた当然の帰結であった。
わが国では1962年、国土を総合的に利用・開発・保全し、産業立地の適正化を図るという総合的かつ基本的な計画として、「全国総合開発計画」が策定された。次第に開発機能も再生機能も失いつつ、50年以上続けられてきたのであるが、1990年のバブル崩壊後、国家財政の厳しさと国民による公共工事批判の声に押されて、公共工事は縮小されていく。地方経済が公共事業に依存する体質を長年にわたってつくりあげてきたのであるから、カンフル剤が減らされると地方が急速に疲弊していくのは当然の成り行きであった。
2002年、小泉構造改革のもとで「三位一体改革」が提案され、新自由主義路線に沿って公共事業の縮小、社会保障の増額抑制、「小さな政府」にする方策がとられた。財政出動は無駄な公共工事を増やすだけで、景気刺激効果はないという見解であった。いわゆるケインズ政策批判である。
小泉政権(2001~2006年)は、公共事業の経済効果がなくなり、財政が行き詰まったので、やむなくこれを縮小する方向をとったものの、それは代替策のない地方の切り捨てであるから、これまでにも増して地方経済を悪化させてしまった。
もともと地方で雇用を吸収する産業は、農林水産業のような第一次産業の家族小経営であり、その他非農林水産業基盤の自営業や、中小企業の製造業、生活密着型の流通・サービス業である。高度経済成長以来、これらの産業を育成する政策は放置して、公共事業による土木・建設業をもって地方経済を変質させてきた。
そこへ小泉構造改革は追い討ちをかけるようにして産業の空洞化を促進させ、これら多種多様な中小・零細の雇用産業を衰退させ、若者が住める場所を地方から奪ってしまった。地方都市では大型店舗の進出によって、商店街は見るも無惨にさびれていった。
2013年6月発表の「日本再興戦略」で全体像が示された「アベノミクス」。大胆な「金融緩和」、放漫な「財政出動」、巨大企業主導の旧態依然たる輸出・外需依存の「成長戦略」という、とうに使い古されたこの「三本の矢」で、相も変わらず経済成長を目指したこの経済政策も、戦後79年におよぶ付けとも言うべき日本社会、なかんずく地域社会の構造的破綻の根本原因にまともに向き合おうともせず、ただひたすら当面のデフレ・円高脱却、そして景気の回復をと、その場凌ぎの対症療法を繰り返すだけに終わった。
小泉構造改革以来今日に至るまで、雇用の不安定化が進行し、今や非正規雇用は雇用者の4割(約2100万人)に達し、特に若者世代では半数にもおよぶようになった。国税庁の2019年調査によれば、民間企業で働く正社員の平均年収503万円に対して、非正規雇用の平均年収は175万円で、何とその格差は328万円にもなっている。しかも正社員であっても、国際的な産業構造の変化に伴い、もはや安泰とは言えない不安に苛まれている。
一方、福祉・年金・医療・介護など、庶民の最後の砦ともいうべき社会保障制度は、機能不全に陥り、破綻寸前にある。競争と成果主義にかき立てられた過重労働、広がる心身の病。特に1998~2011年の自殺者数は、14年連続で年間3万人を超えた。家族や地域は崩壊し、子どもの育つ場の劣化が急速にすすんでいった。雇用破壊は実に深刻な問題を人間精神と社会の根深いところにまで広げていった。
高度経済成長と1970年代からはじまった「経済の金融化」の過程で、日本の国土の産業構造と社会の体質は根底から大きな変質を遂げていったのである。
そして2020年新型コロナウイルスは、目先の利得に囚われ、人為的に延々とつくりあげられてきたわが国の社会の脆弱な体質に、突如、容赦なく襲いかかってきたのである。
国民生活が逼迫する中、2022年、暮れも押し迫る12月16日、岸田文雄首相(当時)は、「安全保障関連3文書」なるものをそそくさと閣議決定した。その驚くべき内容たるや、「敵基地攻撃」能力に巨費を投入、米国製巡航ミサイル「トマホーク」の導入、「無人アセット防衛能力」の構築、武器輸出制限の緩和、促進などなど、2023年度から5年間の軍事費総額43兆円というものであった。
常日頃から、如何にも庶民の味方であるかのように、「聞く耳がある」と嘯(うそぶ)く岸田前首相は、平和を願う国民の切実な声を踏みにじり、米国巨大政権の走狗となって、なりふり構わずウクライナ「人道支援」を掲げ、2023年3月、隠密に首都キーウを電撃訪問。戦争当事国に日本の首相が訪れるのは、戦後初めてのことであった。
ウクライナ、ロシア双方に連日連夜、多数の戦死傷者が続出しているまさにその激戦地で、岸田首相(当時)は、無神経にもゼレンスキー大統領に、「敵を飯(めし)とる=召し捕る」という云われの地元・広島の縁起物「必勝しゃもじ」を贈ったという。これが、世界に誇る「非武装・非戦、非同盟・中立、世界平和」の憲法を持つ国の首相なのである。
「今日のウクライナは明日の東アジア」などと国民の不安を煽り、「アジア版NATO」を提唱する石破茂新首相。
私たちは、決して一方の権力の側に立ち、国際社会に分断と対立を持ち込むようなことがあってはならない。これが、日本国憲法の世界に誇る理念であり、国是ではなかったのか。
残念ながら、自民党政権による戦後長きにわたる憲法違反の既成事実の狡猾な積み重ねによって、政治家のみならず、多くの国民もすっかり麻痺させられてしまったようだ。
石破首相が提唱するこの「アジア版NATO」は、こともあろうに、戦後、自民党政権が抱き続けてきた究極の宿願であり、総決算でもあるのだ。
まさしくそれは、米国との核共有を狙い、東アジア、東南アジア諸国、太平洋島嶼国の民衆をこの新たな核威嚇のもとで、再び戦争の惨禍の泥沼に引きずり込む、戦後これまでにできなかった、実に大掛かりで大胆不敵な極悪非道の謀略そのものなのだ。
一方、選挙民に対しては、集票目当てに、「国民を守る」「地方を守る」などと本音とは真逆の綺麗事を連呼しつつ、自らの党内での根深い不安定要因を解消すべく、ここで敢えてこの禁じ手を持ち出す。そこには恐るべき野望が隠されているのである。
権力の座に就くなり、ことごとく前言を翻し、豹変する。「苦しい時の神頼み」とばかりに、これらすべてを仲間同士「よし」として受け容れ、平然と嘘を弄び、恥じない。
これが、この腐り切った政治集団の末路なのである。
危険極まりない、社会、経済、政治、思想のこんなどん底があっていいのだろうか。
このままでは、もう後戻りできなくなってしまう。
近代経済学を超えて、「地域生態学」的理念と方法を基軸に21世紀の未来社会論を
この際、古典派、新古典派、ケインズ理論、新自由主義に至る百数十年間の経済学の歩みを一括して近代経済学として捉えるならば、まさにそれは、マルクス経済学とは異なり、人類史的長期展望に立った歴史観の欠如を特徴としている。
したがって、資本主義経済を所与のものとして捉え、その本質を問わず、その下での原因結果の「精密科学」を志向しようとするために、部分に埋没して総体を見失い、今日の体制を無批判的に受け入れるという致命的な弱点を持っている。そしてそれは、金融および財政の枠内での分析手法とあれこれの処方操作に特化した、実に狭隘な「市場経済論」に収斂して行かざるを得ない宿命を背負わされている。
その結果、極端なまでの「経済の金融化」を許し、それを増長させてきたこれら近代経済学の根底に流れる思想は、プラグマティズムの思想とも言うべきものであり、人間欲望の絶対的肯定である。これに深く根ざしたこの経済理論は、結果的には人間の欲望を無限に肥大化させ、人間精神をことごとく荒廃へと導き、果てには世界を紛争と戦乱の液状化へと陥れていく震源地にほかならない。このことは、今日の世界の現実を直視さえすれば頷けるはずだ。
この章では、近代経済学を特にケインズ理論とその批判として現れてきた新自由主義を中心に、その特徴をきわめて大づかみに概観してきた。
なかでも、近年顕著に日本経済への提言を行ってきたポール・クルーグマンの近年の一連の著書(『恐慌の罠』、『世界大不況からの脱出』、『そして日本経済が世界の希望になる』)を吟味するならば、その主張の主な内容は、デフレスパイラルに陥っているのであれば、国民に「将来、インフレが起きる」と確信させ、実質金利を下げることによって、「流動性の罠」からの脱出は可能であるとしている点に集約される。新古典派、ケインズ理論等すでに使い古された金融・財政上のあらゆる手法をない交ぜにして、装いも新たに登場してきた考えであることが読み取れる。そこには、近代経済学の行き着く先の末路が暗示されているとともに、その本質と性格が如実にあらわれている。
ここで一括して概観してきた近代経済学は、その時々の対症療法的処方箋を一時凌ぎに提示し得たとしても、経済・社会そして政治的側面をも全一体的(ホリスティック)に捉え、経済・社会、なかんずく「地域生態」の構造的矛盾を歴史的に分析し、そこから次代の新しい萌芽を発見し、そこに依拠しつつ未来社会を展望する理論にまで昇華することは、その本質から言ってもあり得ないことであった。
むしろ資本主義を永遠不変の社会と見なし、それ自体を矛盾の運動体として捉えようとはしないのである。そして現実社会が「末期重症」に陥っていても、自らはこの「永遠不変」の幻想を抱き続け、ひたすら対症療法的延命策に熱中し、社会の体質そのものを根本から変える徹底した原因療法を飽くまでも避けようとする。
そして、多くの人々にも資本主義の永遠不変性への期待と幻想を振り撒き、主観的意図はともかく、客観的には社会を断崖絶壁の淵へと誘うはなはだ危険な役割を演じ続けてきたと言うほかない。
岸田前政権が喧伝し、石破新政権も継承するとした「新しい資本主義」などは、その典型の最たるものである。まさにそこに、近代経済学の階級的性格と、そこから来る本質的な限界を見る思いがする。
と同時に、近代経済学が今なお大手を振って罷り通り、その拠って立つ思想が、経済学者やエコノミスト、そして為政者や経済界のみならず、市井の生活の中にまで深く滲透し、人々の日常普段の思考と行動規範を著しく歪めている現状を見るに、この章の冒頭で項目として掲げたフレーズ「近代を超えて新たな地平へ」、つまり近代を超克する自然循環型共生社会(じねん社会)への構想それ自体を阻む、私たち自身の足下の思想的土壌が、いかに分厚く、根深いものであるかを思い知らされるのである。
今後、近代経済学を経済思想史的側面からも学説史的に整理・考察し、その限界を明らかにすることは、きわめて大切な課題であると痛感している。本章のテーマに掲げた「末期重症の資本主義と機能不全に陥った近代経済学」という視点からのさらなる作業と考察は、あらためて別の機会を得て、現実社会の具体的な歴史過程と照合しながら検証していきたい。
こうした中で、21世紀の未来社会論は、何よりも自然と大地を基底に据え、政治、経済、社会、文化、科学技術、そして思想をも全一体的(ホリスティック)に捉えたいっそう精緻な理論に深められ、あるべき未来社会への具体的アプローチのプロセスも、より精巧なものになっていくにちがいないと思っている。
それが21世紀、私たちがめざす革新的「地域生態学」の理念と方法論に基づく“生命系の未来社会論”であり、その具現化の道筋をも明示した「菜園家族」社会構想なのである。
◆「いのち輝く共生の大地」第4章の引用・参考文献◆
金子貞吉『現代不況の実情とマネー経済』新日本出版社、2013年
J.M.ケインズ『雇用・利子および貨幣の一般理論』東洋経済新報社、1995年
ポール・クルーグマン『恐慌の罠 ―なぜ政策を間違えつづけるのか』中央公論新社、2002年
クルーグマン『世界大不況からの脱出 ―なぜ恐慌型経済は広がったのか』早川書房、2009年
クルーグマン『そして日本経済が世界の希望になる』PHP新書、2013年
――― ◇ ◇ ―――
★ 長編連載「いのち輝く共生の大地 ―私たちがめざす未来社会―」の≪ 総目次一覧 ≫は、下記リンクのページをご覧ください。
https://www.satoken-nomad.com/archives/4114
☆ 読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。
2024年10月18日
里山研究庵Nomad
小貫雅男・伊藤恵子
〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地
里山研究庵Nomad
TEL&FAX:0749-47-1920
E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com
(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)
里山研究庵Nomadホームページ
https://www.satoken-nomad.com/
菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページ
https://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/