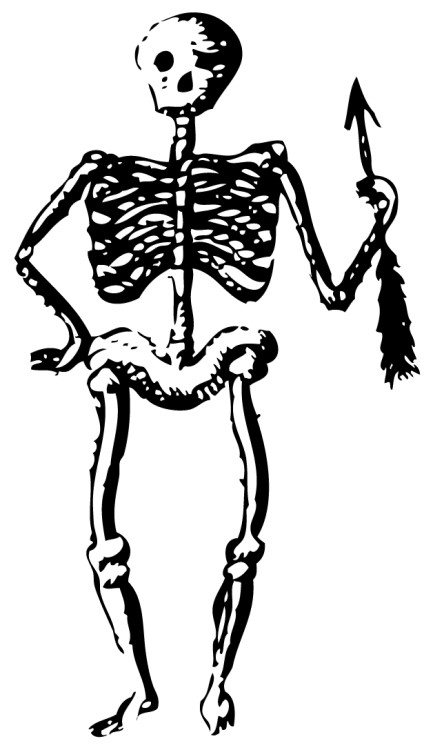連載“高次自然社会への道” 終了にあたって≪1≫
連載“高次自然社会への道” 終了にあたって≪1≫
今や猶予なき喫緊の国民的課題
「菜園家族」を土台に築く近代超克の先進福祉大国 ①
―高次の新たな社会保障制度の探究―
◆ こちらからダウンロードできます。
連載 “高次自然社会への道” 終了にあたって≪1≫
「菜園家族」を土台に築く近代超克の先進福祉大国 ①
(PDF:544KB、A4用紙8枚分)
本来、社会保障制度は社会的弱者に対してこそ、しっかりとした支えになるべきであるのに、わが国の現状はそうはなっていない。その実態は、あまりにも無慈悲で冷酷である。
しかも現行の制度は、不完全な上に、とりわけ年金、医療、介護、育児、教育は、なぜか財政破綻に瀕している。安心して生涯を全うできないのではないかという将来不安や不満が、常に国民の中に渦巻いている。
そもそも社会保障制度とは原理的に一体何であり、どうあるべきなのか。そもそも論から考えるためにも、大切なことなので、まずこのことをおさえることからはじめたい。
1 原理レベルから考える「自助、共助、公助」
今日私たちは残念ながら、人類が自然権の承認から出発し、数世紀にわたって鋭意かちとってきた、1848年のフランスにおける2月革命に象徴される理念、自由・平等・友愛の精神からは、はるかに遠いところにまで後退したと言わざるをえない。
不思議なことに、近年、特に為政者サイドからは、「自立と共生」とか、「自助、共助、公助」という言葉がとみに使われるようになってきた。
「自立と共生」とは、人類が長きにわたる苦難の歴史の末に到達した、重くて崇高な理念である自由・平等・友愛から導き出される概念であり、その凝縮され、集約された表現であると言ってもいい。
それは、人類の崇高な目標であるとともに、突き詰めていけば、そこには「個」と「共生」という二律背反のジレンマが常に内在していることに気づく。
あらゆる生物がそうであるように、人間はひとりでは生きていけない。人間は、できる限り自立しようとそれぞれが努力しながらも、なおも互いに支えあい、助けあい、分かちあい、補いあいながら、いのちをつないでいる。「個」は「個」でありながら、今この片時も、また時間軸を加えても、「個」のみでは存在しえないという冷厳な宿命を、人間は背負わされている。
それゆえに、人類の歴史は、個我の自由な発展と、他者との「共生」という二つの相反する命題を調和させ、同時に解決できるような方途を探り続けてきた歴史であるとも言えるのではないだろうか。
私たち人類は、その歴史の中で、ある時は「個」に重きを置き、またある時はその行き過ぎを補正しようとして「共生」に傾くというように、「個」と「共生」の間を揺れ動いてきた。この「自立と共生」という人類に課せられた難題を、どのような道筋で、どのようにして具現するかを示すことなく、この言葉を呪文のように繰り返しているだけでは、空語を語るに等しいといわれても、致し方ないであろう。
生きる自立の基盤があってはじめて、人間は自立することが可能なのであり、本当の意味での「共生」への条件が備わる。人間を大地から引き離し、人間から生きる自立の基盤を奪い、その上、最低限必要な社会保障をも削って放置しておきながら、その同じ口から「自立と共生」を説くとしたならば、それは、二重にも三重にも自己を偽り、他を欺くことになるのではないだろうか。
ところで、きわめて大切な歴史認識の問題として、ここであらためて再確認しておきたいことがある。それは、イギリス産業革命以来二百数十年の長きにわたって、人間が農地や生産用具など必要最小限の生産手段さえ奪われ、生きる自立の基盤を失い、ついには根なし草同然の存在になったという、この冷厳な歴史の事実についてである。
19世紀「社会主義」理論は、生産手段を社会的規模で共同所有し、それを基礎に共同運営・共同管理することによって「自立と共生」を実現し、さらには資本主義の宿命的根本矛盾、すなわち繰り返される不況と恐慌を克服しようとした。
しかし、20世紀に入ると、その実践過程において、人々を解放するどころか、かえって「個」と自由は抑圧され、「共生」が強制され、独裁専制強権的な中央集権化の道を辿ることになった。人類の壮大な理想への実験は、20世紀末、結局、挫折に終わった。
そして、いまだにその挫折の本当の原因を突き止めることができず、新たなる未来社会論、つまり19世紀未来社会論に代わる21世紀の未来社会論を見出せないまま、人類は今、海図なき時代に生きているのである。
21世紀の今もなお、私たちのこの社会は、大量につくり出されてきた根なし草同然の人間、すなわち近代賃金労働者によって埋め尽くされたままである。大地から引き離され、生きる自立の基盤を失った根なし草同然の人間が増大すればするほど、当然のことながら、市場原理至上主義の競争は激化し、人々の間に不信と憎悪が助長され、互いに支えあい、分かちあい、助けあう精神、友愛の精神、つまり人類始原の原初的「共感能力」(慈しむ心)は、ますます衰退していく。
そしてそれは、個々人間(ここじんかん)のレベルの問題にとどまらず、社会制度全般にまで波及していく。さらには民族と民族、国家と国家間の憎しみ、そして人間同士が殺し合う忌まわしい戦争にまで至るのである。
生きる自立の基盤を奪われ、本来の「自助」力を発揮できない人間、すなわち、近代の負の遺産とも言うべき根なし草同然の賃金労働者によって埋め尽くされた社会をそのままにして、なおも私たちが「共生」を実現しようとするならば、社会負担はますます増大し、年金、医療、介護、育児、教育、障害者福祉、生活保護などの社会保障制度は財政面から破綻するほかない。それが今日、日本社会をはじめ先進資本主義諸国の直面する偽らざる実態なのである。
この事態を避けるために、社会保障の財源と称して、為政者によってさらに強行されようとしている消費税増税は、弱者を切り捨て、巨大資本の生き残りを賭けた愚策にすぎないものであり、もちろん論外であるが、別の選択肢として一般的に考えられるのは、財政支出の無駄をなくすか、所得税等々の累進課税をはじめとする税制の民主的改革によって税収を増やす以外にないことになる。
しかしこれとて、市場経済のグローバル化が際限なく加速し、市場競争がますます熾烈化の一途を辿っていく中にあっては、根なし草同然の賃金労働者家族、つまり市場原理に抗する免疫力を失った従来型の家族を基礎に置く社会を前提にする限り、いずれ遠からず立ち行かなくなるにちがいない。
急速に進行する少子高齢化の中で、もちろん財政の組み替えや節減、そして大企業に459兆円(2019年度)もの内部留保の累積を許すような不公正な今日の税制・財政を抜本的に改革することは、当然貫徹させなければならない当面の重要課題ではあるが、遠い未来を見据える視点に立てば、生産と暮らしのあり方、それに規定される「家族」や「地域」のあり方、つまり近代に特有の今日の社会構造の根源的変革を抜きにしては、こうした短期的処方箋では、もはやどうにもならないところにまで来ていると言わざるをえない。
このような施策は、社会経済構造全体から見れば、もはや表層のフローにおけるきわめて近視眼的な一時凌ぎの処方箋にすぎないものなのである。それは決して今日の深刻な事態を歴史的に位置づけ、長期展望のもとに、この社会の構造的行き詰まりをその深層から根本的に解決するものにはなりえない。
また、「成長戦略」とか「エコ産業」などという触れ込みで、万が一、「経済のパイ」を大きくし、企業からの税の増収をはかることができたとしても、この市場原理至上主義「拡大経済」路線そのものが、本質的に資源の有限性や地球環境問題、ひいては人間性そのものと真っ向から対立せざるをえない。
「環境技術」の開発によって、地球環境問題は解決できると期待する向きもあるようだが、それは幻想に過ぎず、一時の気休めに終わるのではないだろうか。
なぜなら、浪費が美徳の「拡大経済」の根底にある市場競争至上主義の社会システムとその思想そのものを根源的に変えない限り、「環境技術」開発による新たな生産体系そのものが、新たなる法外な「環境ビジネス」を生み出し、資源やエネルギーの消費削減どころか、21世紀型のさらなる新種の「拡大経済」へと姿を変えるだけに終わらざるをえないからである。
しかも、グローバル経済を前提にする限り、「エコ」の名のもとに、市場競争は今までにも増して熾烈を極めていく。国内需要の低迷が続く中で世界的な生産体制の見直しを進める多国籍巨大企業は、「国際競争に生き残るために」という口実のもとに、安価な労働力と新たな市場を求めて海外移転を進め、いとも簡単に国内の雇用を切り捨てる。そしてますます社会的負担を免れようとして、結局はその負担を庶民への増税として押しつけてくる。この繰り返しである。
したがって、自立の基盤を奪われ、「自助」力を失い、根なし草同然になった現代賃金労働者(サラリーマン)家族を基礎単位に構成される今日の社会の仕組みをそのままにしておいて、「自助」を押しつけるための口実に「自立と共生」を語ること自体が、もはや許されない時代になってきていることに気づかなければならない。
21世紀生命系の未来社会論具現化の道としての「菜園家族」社会構想は、こうした時代認識に基づいて提起されている。そして、人類共通の崇高な理念であり目標でもある自由・平等・友愛、つまり「自立と共生」という命題に内在する二律背反のジレンマをいかにして克服し、その理念をいかにして具現することが可能なのか、その方法と道筋を具体的に提起しようとしているのである。
“高次自然社会への道”(その1)において先に提起した“21世紀の労働運動と私たち自身のライフスタイル ―「菜園家族」の新しい風を”、および“「菜園家族」型ワークシェアリングと21世紀労働運動の革新”の視点に加え、この「社会保障制度の問題」との関連でも、主体としての私たち自身の労働と労働運動のあり方を、根本から捉え直さなければならない時に来ているのではないだろうか。
2013年2月28日、安倍晋三首相(当時)は施政方針演説の中で、自助・自立を第一に、共助と公助を組み合わせ、弱い立場の人を援助するとしながらも、「『強い日本』。それを創るのは、他の誰でもありません。私たち自身です。『一身独立して一国独立する』。私たち自身が、誰かに寄り掛かる心を捨て、それぞれの持ち場で、自ら運命を切り開こうという意志を持たない限り、私たちの未来は開けません」、こう述べ、敢えて自助の精神を喚起した。
新型コロナウイルスへの対応で国民の支持を失い、2020年8月28日ついに退陣を表明するに至った安倍元首相の継承を自認もし、公言もして憚らなかった菅義偉前首相は、自民党総裁選のさなかから早々と、自らのめざす社会像として「自助・共助・公助、そして絆」を掲げ、恥じなかった。その意図がどこにあるかは、説明するまでもなく明々白々である。
私たち社会の底知れぬ構造的矛盾に正面から向き合い、大胆にメスを入れ、今日の社会の枠組みを根本から転換することなしに、「自立と共生」、「自助、共助、公助」を説くとすれば、それは大多数の国民を欺き、自立の基盤を保障せずに社会保障をも削減し、自助努力のみを強制するための単なる口実に終わらざるをえない。
2021年10月4日、「新しい資本主義」を掲げ、「成長と分配の好循環で新たな日本を切りひらく」と、装い新たに発足した岸田文雄内閣。これからどんな政権が新たに登場しようとも、社会のこの構造的根本矛盾、つまり生産手段を奪われ、根なし草同然になった近代賃金労働者という人間の社会的生存形態を放置し、市場原理に抗する免疫力を失った家族をそのままにしておく限り、まことの「自立と共生」実現への具体的かつ包括的な道は、見出すことはできない。そうした政権は、遅かれ早かれいずれ国民から見放されるほかないであろう。
2 「家族」に固有の機能の喪失とこの国破綻の根源的原因
もともと「家族」には、育児・教育・介護・医療など、人間の生存を支える細やかで多様な福祉の機能が、未分化の原初形態ではあるが、実にしなやかに備わっていた。これらの機能は、「家族」から「地域」へと拡延し、見事に多重・重層的な相互扶助の地域コミュニティへと形づくられ、人々の暮らしの中に深く根付いていた。
ところが、こうした家族機能の細やかな芽は、戦後高度経済成長の過程でことごとく摘み取られていった。人間にとって本来自分のものであるはずの時間と労働力は、そのほとんどが企業に吸いとられていった。
「家族」は人体という生物個体の、いわば一つ一つの細胞に譬えられる。周知のように、一つの細胞は、細胞核と細胞質、それを包む細胞膜から成り立っている。遺伝子の存在の場であり、細胞それ自体の生命活動全体を調整する細胞核は、さしずめ「家族的人間集団」になぞらえることができる。
一方、この細胞核(=家族的人間集団)を取り囲む細胞質は、水・糖・アミノ酸・有機酸などで組成され、発酵・腐敗・解糖の場として機能するコロイド状の細胞質基質と、生物界の「エネルギーの共通通貨」ATP(アデノシン三リン酸)の生産工場でもあるミトコンドリアや、タンパク質を合成する手工業の場ともいうべきリボゾームなど、さまざまな働きをもつ細胞小器官とから成り立っている。
つまり、一個の細胞(=「家族」)は、生きるに最低限必要な自然と生産手段(農地、生産用具、家屋など)を必要不可欠のものとして自己の細胞膜の中に内包していると、捉えることができる。
したがって、「家族」から「自然」や生産手段を奪うことは、いわば細胞から細胞質を抜き取るようなものであり、「家族」を細胞核と細胞膜だけからなる「干からびた細胞」にしてしまうことになる。イギリス産業革命にはじまる近代の落とし子とも言うべき賃金労働者の家族は、まさしく生産手段と「自然」を奪われ、「干からびた細胞」になった家族なのである。
生物個体としての人間のからだは、60兆もの細胞から成り立っていると言われている。これらの細胞のほとんどがすっかり干からびていく時、人間のからだ全体がどうなるかは、説明するまでもなく明らかであろう。人間の社会も同じである。
高度経済成長は、わが国においてまさに無数の「家族」から生きるに最低限必要な生産手段(農地、生産用具、家屋など)と「自然」を奪い、徹底してこうした「干からびた細胞」にしていく過程でもあった。かつて日本列島の北から南までをモザイク状に覆い、息づいていた森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)では、高度経済成長以降、急速に賃金労働者家族、つまり「干からびた細胞」同然の家族が増えつづけ、充満していった。
国土の産業配置とその構造の劇的変化は、農山漁村から都市への急激な人口移動を引き起こし、農山漁村の過疎・高齢化と都市部の過密化、そして巨大都市の出現をもたらした。近代の落とし子とも言うべき賃金労働者は、大地から引き離され根なし草同然となって都市へと流出し、森と海を結ぶ流域循環型の豊かな地域圏(エリア)は急速に衰弱していった。
その結果、「家族」と「地域」にもともと備わっていた多様できめ細やかな福祉機能は衰退していった。それらのすべてを社会が代替できるかのように、あるいはそうすることが社会の進歩であるかのように思い込まされ、家族機能の全面的な社会化へと邁進していった。まさにこのことが社会保障費の急速な増大と「先進国病」とも言われる慢性的財政赤字を招く重大かつ根源的な要因となったのである。
その上、今やわが国経済は、長期にわたり成長、収益性の面で危機的な状況に陥っている。この長期的停滞は、設備投資と農山漁村から都市への労働移転を基軸に形成・累積されてきた過剰な生産能力を、生活の浪費構造と輸出拡大と公共事業で解消するという戦後を主導してきた蓄積構造そのものが、派遣労働やパート等の非正規・不安定雇用の苛酷な格差的労働編成、そして金融規制緩和のさらなる促進をもってしても、もはや限界に達したことを示している。そこへ襲ったのが2020年新型コロナウイルスである。
経済成長が停滞した今、賃金を唯一の命綱に生き延びてきた「干からびた細胞」同然の賃金労働者家族は、刻一刻と息の根を止められようとしている。家族が「自然」から乖離し、生きるに必要な最低限度の生産手段(農地、生産用具、家屋など)を失い、自らの労働力を売るより他に生きる術のない状況で、職を求めて都市部へとさまよい出る。しかも都市部においても、かつての高度経済成長期のような安定した勤め口はもはや期待できない。
こうした無数の衰弱し切った家族群の出現によって、都市でも地方でも地域社会は疲弊し、経済・社会が機能不全に陥り、息も絶え絶えになっていく。これがまさに現代日本にあまねく見られる地域社会の実態なのである。
そればかりではない。少子高齢化は驚くほどのスピードで加速し、子育ての問題、介護・医療・年金問題はますます深刻になっていく。これが今日の日本をいよいよ危機的閉塞状況に陥れている根本の原因である。
3 「家族」に固有の福祉機能の復活と「菜園家族」を土台に築く高次社会保障制度
私たちは、今に至っても相も変わらず景気の好循環なるものを求めて、目先のあれこれの対症療法に汲々としている状況から、一日も早く脱却しなければならない。そうこうしているうちに、社会もろとも衰退と混迷のどん底に落ちていく。
21世紀、生命系の未来社会論具現化の道である「菜園家族」社会構想では、シリーズ“21世紀の未来社会”(2022年9月~12月、本ホームページに連載)の第五章「19世紀未来社会論のアウフヘーベン ―自然と人間社会の全一体的検証による―」で述べた、革新的「地域生態学」の理念と方法論を基軸に、こうした問題を具体的にどう解決していこうとしているのであろうか。
ここであらためて強調しておきたい。私たちは「干からびた細胞」(=賃金労働者家族)で充満した都市や農山漁村の脆弱な体質そのものを根本から変えなければならない時に来ている。細胞質を失い、細胞核と細胞膜だけに変わり果てた「干からびた細胞」同然の今日の賃金労働者家族に細胞質を取り戻し、生き生きとしたみずみずしい細胞、すなわち「労」「農」一体融合の「菜園家族」に甦らせることからはじめなければならないのである。
今日のわが国社会の客観的状況や条件からも、その可能性はいよいよ大きくなってきている。あとは変革主体の力量如何にかかっている。これは、イギリス産業革命以来、二百数十年にしてようやく辿り着くことのできた、近代を経済・社会の基層から根源的に超克する社会変革の稀に見る好機とも言えよう。
しかもこの社会変革は、上からではなく、民衆自身が自らの生活の場において、主体的に時間をかけ自らの力量を蓄積しつつ、社会の基層からじっくり変えていく、まさしく民衆主体の“静かなる「菜園家族」レボリューション”とも言うべきものなのである。
「菜園家族」を基調とするCFP複合社会では、社会保障制度は一体どのようなものになるのだろうか。まず次のことをしっかりおさえておこう。
CFP複合社会においては、社会の土台を構成する家族が、基本的には賃金労働者と生産手段(自足限度の小農地、生産用具、家屋等々)との再結合によって新たに創出される「菜園家族」であるという点である。すでに述べてきたように、「菜園家族」は、「労」「農」一体融合の自給自足度のきわめて高い、したがって抗市場免疫に優れた自律的な家族である。
それだけではない。週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリング(但し1≦α≦4)によって、老若男女あらゆる世代の人々が家族の場や地域に滞留する時間は飛躍的に増大し、男性の「家庭・地域参加」と女性の「社会参加」が実現されていく。その中で、育児・教育・介護・医療など家族に固有の機能も見事に復活していくのである。
このことは、何を意味しているのであろうか。それは、大地から引き離され、「干からびた細胞」となった賃金労働者を社会の土台に据え、その基盤の上に築かれた従来の社会保障制度が、無慈悲・冷酷、かつ不完全である上に、財政破綻に陥っているのとは対称的に、「労」「農」一体融合の抗市場免疫に優れた「菜園家族」を土台に設計される新たな社会保障制度は、旧制度のこの決定的な欠陥の根本原因を除去しつつ、さらに人間性豊かな高次の福祉社会へと連続的に発展していく可能性が秘められているということなのである。
誤解に基づく一般的な懸念として、「菜園家族」基調のCFP複合社会は、縮小再生産へと転落していくのではないかという見方もあるが、果たしてそうなのであろうか。
“高次自然社会への道”(その7)で詳述したように、むしろ新たな自然循環型共生社会にふさわしい、身の丈に合った高次の「潤いのある小さな科学技術体系」の生成・進化が期待され、これを基礎に、これまでとは異次元の、きめ細やかで多彩かつ豊かな生産能力が自らの社会の土壌に甦り、開花していくのである。
この点に注目すれば、「菜園家族」を基調とするCFP複合社会が縮小再生産に向かうという短絡的な思考に基づく懸念は、払拭されるのではないだろうか。
全国各地に散在する幾千万家族にもともとあった、多様できめ細やかな福祉機能が復活し、全面的に開花することによって、その力量と質の総和は、想像をはるかに超える計り知れないものになるにちがいない。しかも、同時並行して「菜園家族」を基軸に多重・重層的な生き生きとした地域コミュニティが形成されていく。
こうした中で、家族や地域コミュニティにしっかり裏打ちされた新たな社会保障制度、すなわち近代をはるかに超える、安定的で持続可能な円熟した新たな高次の社会保障制度の確立が期待されるのである。
こうして、「菜園家族」を基調とするCFP複合社会の長期にわたる展開過程の中で、財政破綻を招く根源的な原因は、社会の基層から次第に除去されていく。つまり、不条理な外的要因によって不本意にも奪われた家族に固有の機能を補填するために費やされてきた、莫大な歳出による国や地方自治体の赤字財政は、近代を超克する「労」「農」一体融合の新たな人間の社会的生存形態、すなわち「菜園家族」を土台に築く、家族や地域コミュニティに裏打ちされたこの新たな高次の社会保障制度のもとで、次第に解消されていくにちがいない。
◆“高次自然社会への道” 終了にあたって≪1≫の参考文献◆
広井良典『日本の社会保障』岩波新書、1999年
広井良典『持続可能な福祉社会 ―「もうひとつの日本」の構想』筑摩新書、2006年
神野直彦『人間回復の経済学』岩波新書、2002年
神野直彦『地域再生の経済学 ―豊かさを問い直す』中公新書、2002年
宮本太郎『貧困・介護・育児の政治 ―ベーシックアセットの福祉国家へ―』朝日新聞出版、2021年
――― ◇ ◇ ―――
★読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。
2024年5月17日
里山研究庵Nomad
小貫雅男・伊藤恵子
〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地
里山研究庵Nomad
TEL&FAX:0749-47-1920
E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com
(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)
里山研究庵Nomadホームページ
https://www.satoken-nomad.com/
菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページ
https://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/