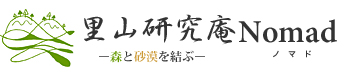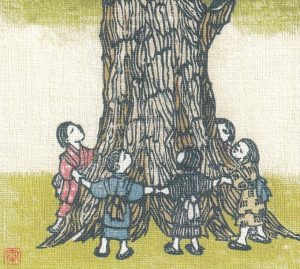長編連載 の終了にあたり、その総括にかえて、後述の「近代(資本主義の時代)を超克する高次国民運動への根源的転換に向けて」を8項目にわたって掲載します。
つまりそれは、―「地域」と「労働」の私たち自身の足もとから築く “21世紀、高次国民運動” への根源的転換―をめざすものです。
2025年、早春を迎え、これを骨子に、あまたの英知に学び、さらなる目標に向かって努めていきたいと思います。
長編連載の≪総括にかえて≫に先立ち、まずは長編連載そのものを振り返り、◆長編連載の核心的根幹◆を簡潔に確認することからはじめたいと思います。
ところで、かつての19世紀未来社会論には、当時の科学研究上の時代的制約から、当然のことながら、大自然界の生成・進化の「適応・調整」の原理(=「自己組織化」)を、自然界と人間社会両者を貫く生成・進化の普遍的原理に止揚し、その普遍的原理を基軸に、未来社会を構想する発想は、残念ながらなかったといってもいい。
今日、「自己組織化」の理論は、とくに自然科学研究の分野においては広く定着しているにも関わらず、その原理を自然界と人間社会両者を貫く全一体的(ホリスティック)な普遍的原理に措定し、19世紀未来社会論を敢然と止揚し、21世紀未来社会論を理念および具体的方法論にわたって構想する例は、管見の限り見当たらない。
こうした今日の未来社会論の現状を根源的に是正すべく試みたのが、この 長編連載 「いのち輝く共生の大地 ―私たちがめざす未来社会―」の内実であり、21世紀“生命系の未来社会論”具現化の道としての「菜園家族」未来社会構想に込められた理念と具体的方法論なのである。
大自然界と人間社会両者の生成・進化を貫く「適応・調整」の普遍的原理(=「自己組織化」)、およびそこから自ずと導き出される“地域生態学”的方法論を二つの大切な基軸にして、この長編連載「いのち輝く共生の大地 ―私たちがめざす未来社会―」は展開されている。
特に、大自然界の生成・進化の原理(=「自己組織化」)、および地域生態学的基軸方法論、これら二つの論点に刮目して、再度、本連載を読み通していただければ幸いである。
◆長編連載の核心的根幹◆
米中露「三超大国」を基軸に
先進資本主義諸国入り乱れての
醜い多元的覇権抗争の時代。
超大国、大国いずれの国においても
国民主権を僭称する
一握りの政治的権力者は
分断と対立と憎しみを煽り
民衆に
民衆同士の凄惨な殺し合いを強制する。
今や世界は生命を蔑ろにして恥じない
倫理敗北の時代に突入している。
今こそ
自然観と社会観の分離を排し
大自然界の生成・進化を貫く
「適応・調整」(=「自己組織化」)の原理を
両者統一の生成・進化の普遍的原理に止揚し
社会変革のすべての基礎におく。
根なし草同然の賃金労働者と
生産手段との「再結合」による
近代と前近代の「労」「農」人格一体融合の
抗市場免疫に優れた
新たな人間の社会的生存形態
「菜園家族」を基礎単位に構築される
21世紀の未来社会構想。
“生命系の未来社会論” 具現化の道としての
この「菜園家族」未来社会構想の根底には
人々の心に脈々と受け継がれてきた
大地への回帰と止揚(レボリューション)という
民衆の揺るぎない歴史思想の水脈が
深く静かに息づいている。
まさにこの民衆思想が
冷酷無惨なグローバル市場に対峙し
大地に根ざした
素朴で精神性豊かな生活世界への
新たな局面を切り拓く。
世界は変わる
人が大地に生きる限り。
人間復活の高次自然社会を展望するこの “生命系の未来社会論” の核心は、とどのつまり、21世紀の今日の現実から出発して、脱資本主義に至る長期にわたるプロセスのいわば中間項に、近代と前近代の「労」「農」人格一体融合の抗市場免疫に優れた社会的生存形態「菜園家族」を基調とするCFP複合社会※ の生成過程を必要不可欠の一時代として措定し、位置づけていることにある。
まさにこの点において、「菜園家族」未来社会構想は、19世紀以来、人類が連綿として探究し続けてきたこれまでの未来社会論に対して、あらためて再考を迫るものになるであろう。
まさしくそれは、19世紀マルクス未来社会論アウフヘーベンの肝心かなめの鍵であり、今日社会の閉塞・混迷自体をも打開する、希望と創意あふれる明日への道でもあるのです。
※ 資本主義セクターC(Capitalism)と、家族小経営セクターF(Family)と、公共的セクターP(Public)の3つのセクターから成る複合社会。
― 長編連載の≪総括にかえて≫ ―
近代(資本主義の時代)を超克する
高次国民運動への根源的転換に向けて
近代巨大建造物は
まさしく音を立て
今や腐蝕と崩落の目前にある。
欺瞞に充ち満ちた
「選挙」の卑小な枠組みに埋没し
権力の術中に陥ることなく
21世紀の新たな人間の社会的生存形態「菜園家族」を土台に
大地に根ざした、いのち輝く民衆主体の
高次国民運動への根源的大転換へ。
◆ こちらからダウンロードできます。
長編連載「いのち輝く共生の大地」
総括にかえて
(PDF:822KB、A4用紙21枚分)
―― ≪総括にかえて≫ の 目 次(8項目) ――
(1)民衆の生活世界を自らの足元から築く
―腐り切ったわが国の「政治」を乗り越えて―
(2)21世紀こそ草の根の変革主体の構築を
―まことの民主主義の復権と「地域」と「労働」の再生―
「お任せ民主主義」を社会の根っこから問い直す
身近な語らいの場から、未来への瑞々しい構想力が漲(みなぎ)る
(3)労働組合運動の驚くべき衰退、そこから見えてくるもの
(4)21世紀の労働運動と私たち自身のライフスタイル ―「菜園家族」の新しい風を―
(5)「菜園家族」型ワークシェアリングと21世紀労働運動の革新
(6)多彩で自由な人間活動の「土づくり」
―次代への長期展望に立った
国民的運動への根源的大転換に向けて―
(7)「お任せ民主主義」を排し、何よりも自らの主体性の確立を
―そこにこそ人間としてまことの生きる喜びがある―
(8)身近な郷土の「点検・調査・立案」の連続らせん円環運動から
“21世紀の未来”が見えてくる
――― ◇ ◇ ―――
―メモランダム風に―
以下8項目
続きを読む →